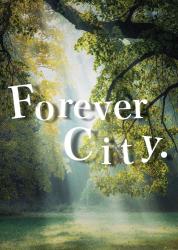父親を殺して、独りになった時。
全てを遊びだと思うようにした時から、全てを振り切ってきたつもりだった。
だけど、どうやらそれは違うらしい。
だから今こうして、彼女と " 遊び " をしている。
「 ねぇ、本当にやめなくていいの? 」
烏禅くんがこの " 遊び " に気づいた時から、俺はいつもこうして彼女…紅苺ちゃんに聞いていた。
まるで、自分に問うように。
そして紅苺ちゃんは、いつも決まって何も言わずに頷く。それに安心を抱いたのか、焦りを抱いたのかは、毎回分からないまま。
きっとこの " 遊び " には、晴雷さんも狂盛も気付いているんだろう。
「 ごめんね、ちょっと乱暴しちゃった。 」
『 ううん、大丈夫。 』
いつもより少しだけ乱暴な " 遊び " を終えて、紅苺ちゃんに謝った。
布団を被りながら、壁を向いたままそう言う紅苺ちゃん。小さなその背中を見つめていると、ふつふつと罪悪感が込み上げてくる。
きっと、俺がこんな " 遊び " を始めなければ、まだ紅苺ちゃんの目は輝きを残していたのかもしれない。まだ、紗來の頃の自分を残していたのかもしれない。
俺も、紅苺ちゃんも、いつの間にかこの " 遊び " に依存してしまっていた。
やめなければいけないことなんて、分かっていた。けど、やめられない所まで、戻れないところまで来てしまった。
愛を忘れてしまった彼女を見て、俺と似たものを感じてしまったから、仕方が無い。そんな言葉で済ませてしまおうとも思ったけど、このままではそれも駄目になってしまう。
先程まで、吐息とベッドの軋む音が微かに響いていた部屋。
「 喉乾いた、水飲んでくる。 」
『 うん。 』