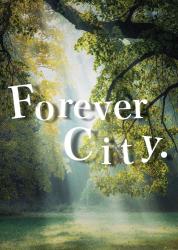あいつらとは、きっと晴、雷さん達三人のことだ。
どうして彼が紅苺さんにそんなことを言ったのかは、白椛さんの口から聞かなくてもら何となく分かっている。
〔 紅苺ちゃんは、あいつらのこと…ちゃんと愛してやってるかな、って。 〕
きっと、白椛さんはその答えを俺に求めている。
だけど俺は、その言葉になんと答えればいいのかが分からなかった。だって紅苺さんは、数日前に " 愛を忘れてしまった " と言っていたから。
言葉を濁すようにして髪を掻けば、〔 ま、何となく分かるけどね。 〕と笑う。
先程の呑気な笑顔とは違った、こちら側の世界の人間が見せる、どこか切なさを帯びるような笑顔だ。どこか物足りなく、どこか儚い、胸が締め付けられるような笑顔。
「 …僕は、紅苺さんのことが好きです。 」
しばらく静寂を味わってから、俺は自分からそう口を開いた。
白椛さんは一瞬だけ目を見開いたものの、直ぐに笑って〔 分かる気がする。 〕と呟く。
〔 良かった、君みたいな子が拾われてくれて。 〕
「 …俺が? 」
そんなこと、初めて言われた…
だって、今まではずっと失望されてきていたから。
されてもいない期待を裏切り、誰からも望まれず、一生面白みのない下らない人生を生きては死んでいくものだと思っていたから。
でもあの時、紅苺さんに出会った。
月に照らされる彼女の横顔は、どんなものよりも美しく、そして何より儚いもので。
彼女を愛したおかげで、俺はこの仕事と出会えることが出来た。新しいものを見つけた。そして、人を愛することを知った。
…紅苺さんの、おかげなんだ。
〔 …その気持ち。絶対に、忘れないようにね。 〕
『 ……はい。 』
彼からの言葉を聞いて、俺は再び紅苺さんを愛し続けることを決めた。