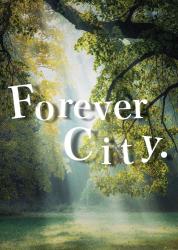むせるほどの、鉄…いや、血液の匂い。
柔らかい、嗅ぎなれた柔軟剤の香りと混ざったそれは、あまりに気味の悪いもので。
急いで靴を脱ぎ捨て、慌ててリビングへと向かった。
「 ッ、母さん!! 」
そこには、真っ赤に染まった母がいた。
首、胸、腹部、足。
白かったはずの肌は、傷だらけになっていた。
急いでその場に駆け寄り、しゃがんで母の身体を起こす。
少しだけ硬く、いつもより冷たくなったその身体は。まるで、気持ち良く眠っているかのように閉じられた瞼は。
もう二度と、動かないのであろうと悟った。
「 ねぇ、母さん。 」
どれだけ揺すっても、返事をしない母。
自分の目から零れ落ちた涙が、母の頬に落ちた。
血液と混ざって赤くなった涙は、頬から床へと流れ落ちる。
「 母さん…起きて。 」
永遠の眠りについてしまった母に、そう呼びかける。
嗚咽混じりのその声は、情けなく震えてしまっていた。
「 ッ…ねぇ、母さん!! 」
一番愛していた人を、亡くしてしまった。
一番愛してくれた人が、死んでしまった。
誰よりも暖かい愛情をくれて、誰よりも僕を愛してくれていた。誰よりも大好きで、愛していて、沢山の愛情を注がれてきた。
柔らかい笑顔ばかり見せていたその顔も。もう一生、感情を表すことのない、人形のようになってしまったのだ。
「 ごめん、ごめんね……守れなくて、ごめん…ッ、母さん…。 」
か細い声は、土砂降りの雨によって掻き消された。