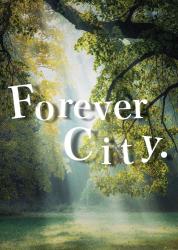物心ついた時から父親はおらず、母は女手一つで僕を育ててくれた。
母は優しくおおらかで、沢山の愛をくれた。そして僕も、母のことを愛していた。
そのおかげで毎日は楽しく、学校生活も充実していた。
そして僕が高校一年の頃、母は僕にこんなことを言ったんだ。
[ ごめんね、澪。お母さん、澪に隠してることがあるの。 ]
改まってそんなことを言ってくるものだから、何なんだろうとは思ったけど。
母は昔から、僕が眠ったのを確認すると[ ごめんね。 ]と小さく呟き、夜になるとどこかへ出掛けていたことを、僕は知ってる。
そして、決まって鉄の匂いを纏って帰ってくる。
母が言いたいことは、何となく分かっていた。
[ …お母さんね、実は、 ]
「 大丈夫だよ、母さん。僕、何となく分かってるから。 」
母の言葉を遮ってそういうと、母は綺麗な顔を歪めて涙を流した。母の泣いた姿を見るのは初めてで、気が動転しながらも泣き崩れた母を抱きしめた。
この瞬間、曖昧にしか分かっていなかったものが、確信へと変わったのだ。
母は、俗に言う " 殺し屋 " らしい。
母の亡くなった親が元々その仕事をしていて、母が受け継ぐことになったのだとか。
その話を聞いて、母が僕に言いたいことは、もう分かっていた。
「 いいよ。僕、やるから。 」
[ …ごめんね、澪。こんなことにあなたを巻き込んでしまって。 ]
そして16歳の梅雨の時期、僕は殺し屋になった。
母の目からは、まるで止むことを知らない雨のように涙が零れ落ちていた。
それはきっと、僕に対する罪悪感のせいだろう。
正直、人を殺すことに関しては何も思わなかった。