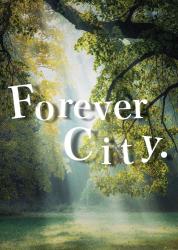別に、この世界が嫌いなわけじゃなかった。
周りの人間に対して、嫌悪感を抱いているわけでもない。同じような毎日がつまらない訳でも無いし、楽しいわけでもない。
ただ、何に関しても興味が持てないだけだった。
楽しいとか、嬉しいとか、怒りとか、悲しいとか。そんなものは、何も知らないまま生きていたんだ。
[ 泪、ご飯出来たわよ! ]
高校一年の終わり、自室で学校での課題をしていると、リビングから母親の声が聞こえてきた。
扉を開けると、ふわりと香ってくる夜ご飯の匂い。
優しい母も、頼もしい父も、嫌いではない。でも、好きなわけでもない。
それは決して、二人と血が繋がっていないことが理由なわけでもなかった。
産まれてから間もなく捨てられた僕は、この二人に引き取られた。
血が繋がっていない、見ず知らずの人捨てられた子供を、二人は、まるで我が子のようにして育ててくれた。
[ 泪。もうすぐ二年生になるけど、学校はどうだ?楽しいか? ]
「 うん、楽しいよ。 」
周りの人間と同じようにそう言って、いつも父や母が見せる笑顔の真似をして見せれば、父も母も同じように笑った。
楽しい、とは、どういうことなんだろう。
何が面白いだとか、この映画が悲しくて泣けただとか。
周りは当たり前のようにしてそんなことを言うけれど、僕にはさっぱり分からなかった。
自分が異常な程に感情を持たない人間だということには、前から気づいていた。
だからってどうしようとも思わないし、他人の真似事をしていれば、他人と同じようにして扱われる。だから僕はいつだって笑えたし、時には怒ることだって出来た。
他人の真似事をして、普通の人間を演じていた。