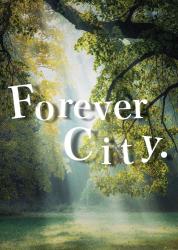あれから数週間、特に変わりのない生活を送っていた。
『 あーあ、今日も暇だね。 』
夜中、俺がリビングでテレビゲームをしていると、紅苺さんがそう言いながら隣に座ってきた。
今日は晴雷さんが仕事に出かけていて、狂盛さんは既に眠りについている。
眠れないし、することがなかった俺は、こうして暇潰しにゲームをしていた。
「 …ですね。 」
微かに游鬼さんの香水の香りを纏った彼女に、俺はそうとだけ答える。そんな匂いで確信するよりも前に、游鬼さんの部屋から聞こえていた音で、全てを察していた。
あれから、今日だけでなく、それまでも何度か二人の音が聞こえてくることはあった。
狂盛さんは『 二人のセックスに、愛なんてものは無いよ 』と言っていて、俺もなんとなく、その言葉には納得していた。
紅苺さんのことだ。自分の欲を満たすために抱かれるような人ではないし、他に何か理由があるんだろう。
「 紅苺さんもやります?ゲーム。 」
『 え〜。私、ゲームとかやったことないからな…。 』
そんなことを言いながら、紅苺さんはもう一つのコントローラーを手に取った。
艶がかった茶色の髪が揺れて、少しだけ俺の腕に当たる。たったそれだけの事に心臓が大きく動きながらも、指は冷静に " GAME STAR " のボタンを押していた。
『 あー……あっ、もう負けた。 』
「 …弱すぎませんか? 」
『 烏禅くんが強すぎるんだよ。ねぇ、もう一回! 』
「 いいですよ。 」
慣れない手つきでコントローラーを握る姿も、負けて悔しがる姿も、どこか可愛らしさを感じた。
" 紅苺 " ではなく、彼女の本来の姿を見ているように感じたんだ。
でも俺は、彼女の本当の名前は知らない。それがもどかしくて、どこか悔しく、寂しかった。