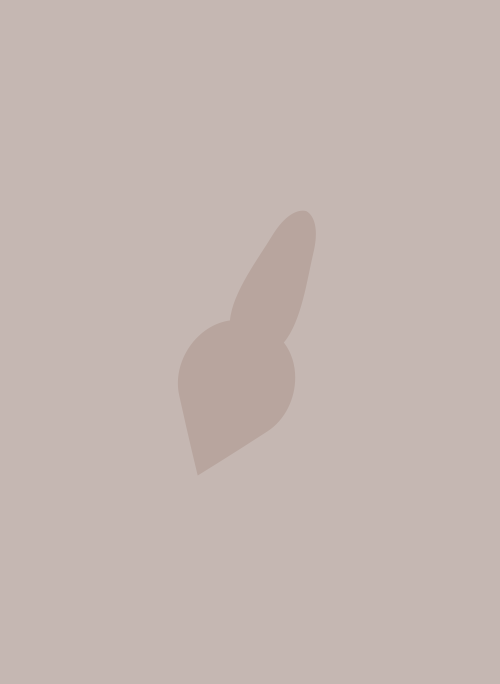シートに伝わる小刻みな振動が必要以上に俺に苦痛を与えようとする。
ズキズキと足と腕の傷に舗装の悪い道の凹凸が響く。
俺は路面の凹凸に合わせる様に体を強張らせる。
時折、木村が怪訝そうな顔で俺の方を見ているのが感じ取れる。
「・・・血」
『・・・んぁ?』
「血が滲んでる・・・ダッシュボードにポケットティッシュ入ってるだろうから」
『あぁ・・・悪い』
「俺は構わねぇが、交通課のネェちゃん達が乗る車なんでね。・・・汚ねぇシミつくったら俺が文句言われるからよぉ」
俺は無言でダッシュボードを開けて、ポケットティッシュを取り出し、傷口から繊維を通して滲み出てくる血を含ませる。
「一生懸命になったって得は無えと思うがねぇ」
『・・・だろうな』
俺はそれ以上木村に何も話す気は無い。
木村も端から俺を諭すつもりは無かっただろうが、現場に着くまでにそれ以上何も俺に問いかける事は無かった。
現場に着くと数人の警官と鑑識の人間が、傍から見ても容易に見当が付くほどヤル気の無い顔でヤル気の無い現場検証をしていた。
木村が交通の邪魔にならない様に、ミニパトを歩道に乗り上げて電柱の前に停める。
ミニパトを歩道に乗り上げる時に、木村は何の躊躇も無く段差に踏み込んだので、俺の体にこの上ない痛みが走り、俺は木村の顔を思い切り張りたい気持ちになったが、それ以上に痛みを耐える事に必死だった。