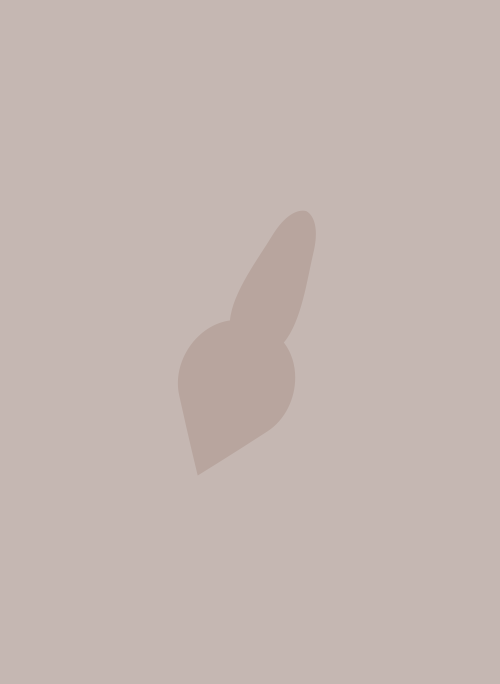―――――ヤマモト
木村は俺が了承したものと安堵し、更にムカつくニヤけた面でコーヒーを啜る。
俺はと言えば、正直まだ悩んでいて、まとまらない考えが頭を巡り、ウエイトレスが波々と注いだままのコーヒーを眺め続けていた。
――ヤクはやらねえ
今の御時世で何とも青臭い考えだとは自分自身でも分かっている。
今時、ヤクを外道と言う奴は極道モンにも居ないに等しい、潤沢な資金を維持する立派なシノギだ。
極道モンに限らずとも、今じゃ猫も杓子もヤクに手を着ける。
現に大久保のシマでは、半島の奴らがイラン人だかイラク人だかを使ってガキ共相手にハッシシやらを手広く捌いていやがるし、職安通りの向こうでは大陸系の奴らが極道モン相手にシノギを削ってやがる。
正直に言ってしまえば、青臭い事言ってたら機を逃し、既にヤクを捌くには手詰まりと言うのが本当のとこで、単純な俺の負け惜しみなのかもしれない。
以前にヤナギが、高田馬場でガキ相手のハッシシのシノギを持ち掛けて来た事があった。
馬場は昔からの学生相手の金貸しで地盤は出来てるし、幸いに同業も少なく悪い話じゃなかった。
その上、良く出来た子分のヤナギは仕入れから何からをしっかりと用意して、その話を俺に持ち掛けた。
だが俺はいつもの悪い癖で意地を張り、ヤナギを殴って一蹴し、そんなシノギをパーにした。
木村は俺が了承したものと安堵し、更にムカつくニヤけた面でコーヒーを啜る。
俺はと言えば、正直まだ悩んでいて、まとまらない考えが頭を巡り、ウエイトレスが波々と注いだままのコーヒーを眺め続けていた。
――ヤクはやらねえ
今の御時世で何とも青臭い考えだとは自分自身でも分かっている。
今時、ヤクを外道と言う奴は極道モンにも居ないに等しい、潤沢な資金を維持する立派なシノギだ。
極道モンに限らずとも、今じゃ猫も杓子もヤクに手を着ける。
現に大久保のシマでは、半島の奴らがイラン人だかイラク人だかを使ってガキ共相手にハッシシやらを手広く捌いていやがるし、職安通りの向こうでは大陸系の奴らが極道モン相手にシノギを削ってやがる。
正直に言ってしまえば、青臭い事言ってたら機を逃し、既にヤクを捌くには手詰まりと言うのが本当のとこで、単純な俺の負け惜しみなのかもしれない。
以前にヤナギが、高田馬場でガキ相手のハッシシのシノギを持ち掛けて来た事があった。
馬場は昔からの学生相手の金貸しで地盤は出来てるし、幸いに同業も少なく悪い話じゃなかった。
その上、良く出来た子分のヤナギは仕入れから何からをしっかりと用意して、その話を俺に持ち掛けた。
だが俺はいつもの悪い癖で意地を張り、ヤナギを殴って一蹴し、そんなシノギをパーにした。