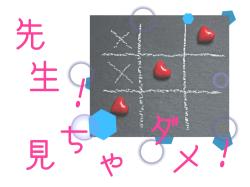そう言った雨月くんの顔が、妙に色っぽくて。
ほとんど反射的に、心臓が高鳴る。同じ高校生とは思えなくて。
なんだか雨月くんの顔を直視できなくて、うつむいてしまう。
「…ごめん、困らせたか?」
心配そうな声で雨月くんが言う。
私がうつむいたのを、困ったからだと勘違いしたようだ。
だけど、「雨月くんの色気がすごすぎて直視できなかっただけです」なんて、恥ずかしくて言えない。
「ううん、困ったわけじゃなくて、」
「…じゃあ、顔上げれば」
「そ…それは無理」
「なんで」
ああ、まただ。また雨月くんを不機嫌にさせてしまった。
…でもどうしても、理由言わなきゃダメだろうか。
「ちょっと今、勝手に恥ずかしくなってて」
「……そ」
てっきり何か追及されるのだとばかり思っていたから、驚いて顔を上げる。