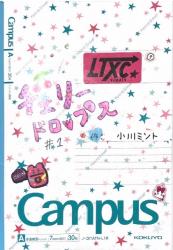私の手を救ってくれる人がいた。
_あなたは神なんです?
そんなことを一瞬でも思った私が駄目だった。
最初。目をうっすらと開けると、ぼんやりと、目の前にはモザイクがかった人が立っていた。
ひ、と?私は目を擦りまどろみの中、その人のことを必死に目を凝らして見る。うんと。
すると、その人は私の手をいきなりぎゅっと握ると、にこりと微笑む。
_女だ。
やっと、そのことに気がついた。
そして伝わってきた手の温もりによって、私はその人が人間なんだと再認識させられた。
_って何?この状況。
そこで、ようやく鮮明になった私の視界にいた、私の手を握ってきた女は。
とてつもなくいかつく見えた。なんだか良く分からないが、刺々したオーラを、彼女は纏っていた。
私は思わず、手をパッと離し一歩引き下がる。
「世に言う不良って奴…?」
細々しい、だが、絶対に相手には聞こえる声で、私は呟いてしまった。
私は唾を飲む。今のは禁句だった、と思うももう遅い。
その瞬間、その女は、けっと苦い顔で吐き捨て、私の手を離す。
「うわー、ないわー。せっかく助けてやったんに」
「助け、て?」
「おん。今、あたいがアンタの手、握ったろ?なんか困ってる風、に見えたから。救ってあげた…んー、あたいはアンタからしてスーパーヒーローっつー訳」
「…」
その女は、相変わらずのいかつい表情で喋っている。
だが、私は助けようとしてくれたその優しさで、少しばかり心のもやもやが消え失せたのを自覚した。
_でも、何でこんな鋭いのよ。“困ってる”って。
「本当、有難いよ?でも、何でそんな分かんの…。もしかしてあなた、メンタリストとか」
「は、正気かよ。あたしは不良。うん。…いや、今のアンタは誰が見ても一目瞭然よ、困ってる。っつーか、悲しいことでもあったんだなって」
私は首をかしげる。
「顔に出てんのよね、要するに。あと体も。明らかにそれはやつれてるよ、分かる」 そう言って彼女は、私の顔を覗き込んだあと、見事に金色に染まった髪を手で無造作にかきあげた。
私は、金髪って染めたらムラになったり大変なんだろうな、等と今の話に関係ないことをぼやっと考えた。
「おい、聞いてんの?てか、アンタ名前何てゆーの。あたいは麻美、高2。この春休みが明けたら高3」
「あ、私は青山すみれ。よろしく」
「そう他人行儀にすんなってすみれ。なにせあたいだって不良成り立てだからさ。わりと親近感アリアリで話せると思うんよ」
「不良成り立て、かぁ。成り立てでも不良は不良でしょ…」
「ま、そこは気にしないで」
私は、不良の麻美さん(?)の眩しい笑顔を眺めながら一人、溜め息をついた。 そうして、空を見上げる_と、もうそこには夕焼けが広がっていた。それは、とても鮮烈な朱色で、何だか人工的な色に思えた。
_この人はなんで。何でこんな笑っていられるの。分かんない。
私はもう何年も、心の奥底から笑っていなかった。というより、もう笑い方すら忘れかけている。今、仮に麻美さんに笑え、と言われても、笑えるかどうか怪しいところだ。
「なぁ、すみれはさ、ポテトってさくさく派or しなしな派、どっち?」
私はいきなりポテトの話を投げ掛けられ、内心驚く。
だが、口では「…中間派、かな」と暗い返し方しか出来なかった。このことに、自分でも驚いた。
麻美さんは、乾いた不良特有の声で、ははっと笑う。
「どっちかつってんだけどー。ま、とにかくあたいはさくさく派っていうのを分かって欲しい。マックとかでさくさくのが沢山入ってると、うっしゃ!って一人喜んでるんですよ」
「まじかー」
「や、まじって思ってる?目が死んだ魚の目のように虚ろだYO ?ミス青山」
「まぁ、私はもう人生死んでっからね」
普通は、このDJ 的な口調に突っ込みを入れたところだろうが、私にはそんな気力は到底なかった。
「ま、人生死んでるかもだけど、アンタはとりま、まだ生きてんじゃん。だからさー。お悩み相談でも何でもあたいにしーよ。心軽くする程度のことなら出来ると思うから」
彼女にとっては何気ない一言だったのかも知れないが、その言葉は私の心に一つの光を灯した。
_不良でも優しい人はいるんだ。ってまだ分かんないけどね。
「考えてみる」
「なんだよー。暗いなー。ま、あたいは、週四回位なら、この芝生に来れっから。んじゃ、シーユー!」
「ば、ばいばい?」
何だかやけに疲れた。私はあくびを噛み殺す。
きっとそれは、不良と話すという、あまりに現実味のない出来事があった為だろう。
私は肩を揉みほぐすと、のろのろと立ち上がった。そうして、スウェット地の服に付いた草を手でぱらりとはらう。
_今日も、上下スウェットというださい格好で来ちゃったよ。まあ良いや、帰ろう。
私はゆっくりとした歩調で、芝生岸の舗装された道路を歩くも、全身が麻痺したかのように感覚がない。
_もしかして私って本当に死んでる?幽霊?で、麻美さんには幽霊が見えるとか…。
そんな下らないことを、私は考えてしまっていた。あり得ない。
すると、いきなり雨がぽつぽつと振りだしてきた。それはすぐに本降りに変わった。
雨は、近くにあった古びた家のトタンの屋根を強く打ち付けている。
「もー、何でこんな時に…」
私は不満を言いつつ走るも、普段走ることなどなかった為、思うように速く走れなかった。日頃の運動不足を痛感した私だった。
_あなたは神なんです?
そんなことを一瞬でも思った私が駄目だった。
最初。目をうっすらと開けると、ぼんやりと、目の前にはモザイクがかった人が立っていた。
ひ、と?私は目を擦りまどろみの中、その人のことを必死に目を凝らして見る。うんと。
すると、その人は私の手をいきなりぎゅっと握ると、にこりと微笑む。
_女だ。
やっと、そのことに気がついた。
そして伝わってきた手の温もりによって、私はその人が人間なんだと再認識させられた。
_って何?この状況。
そこで、ようやく鮮明になった私の視界にいた、私の手を握ってきた女は。
とてつもなくいかつく見えた。なんだか良く分からないが、刺々したオーラを、彼女は纏っていた。
私は思わず、手をパッと離し一歩引き下がる。
「世に言う不良って奴…?」
細々しい、だが、絶対に相手には聞こえる声で、私は呟いてしまった。
私は唾を飲む。今のは禁句だった、と思うももう遅い。
その瞬間、その女は、けっと苦い顔で吐き捨て、私の手を離す。
「うわー、ないわー。せっかく助けてやったんに」
「助け、て?」
「おん。今、あたいがアンタの手、握ったろ?なんか困ってる風、に見えたから。救ってあげた…んー、あたいはアンタからしてスーパーヒーローっつー訳」
「…」
その女は、相変わらずのいかつい表情で喋っている。
だが、私は助けようとしてくれたその優しさで、少しばかり心のもやもやが消え失せたのを自覚した。
_でも、何でこんな鋭いのよ。“困ってる”って。
「本当、有難いよ?でも、何でそんな分かんの…。もしかしてあなた、メンタリストとか」
「は、正気かよ。あたしは不良。うん。…いや、今のアンタは誰が見ても一目瞭然よ、困ってる。っつーか、悲しいことでもあったんだなって」
私は首をかしげる。
「顔に出てんのよね、要するに。あと体も。明らかにそれはやつれてるよ、分かる」 そう言って彼女は、私の顔を覗き込んだあと、見事に金色に染まった髪を手で無造作にかきあげた。
私は、金髪って染めたらムラになったり大変なんだろうな、等と今の話に関係ないことをぼやっと考えた。
「おい、聞いてんの?てか、アンタ名前何てゆーの。あたいは麻美、高2。この春休みが明けたら高3」
「あ、私は青山すみれ。よろしく」
「そう他人行儀にすんなってすみれ。なにせあたいだって不良成り立てだからさ。わりと親近感アリアリで話せると思うんよ」
「不良成り立て、かぁ。成り立てでも不良は不良でしょ…」
「ま、そこは気にしないで」
私は、不良の麻美さん(?)の眩しい笑顔を眺めながら一人、溜め息をついた。 そうして、空を見上げる_と、もうそこには夕焼けが広がっていた。それは、とても鮮烈な朱色で、何だか人工的な色に思えた。
_この人はなんで。何でこんな笑っていられるの。分かんない。
私はもう何年も、心の奥底から笑っていなかった。というより、もう笑い方すら忘れかけている。今、仮に麻美さんに笑え、と言われても、笑えるかどうか怪しいところだ。
「なぁ、すみれはさ、ポテトってさくさく派or しなしな派、どっち?」
私はいきなりポテトの話を投げ掛けられ、内心驚く。
だが、口では「…中間派、かな」と暗い返し方しか出来なかった。このことに、自分でも驚いた。
麻美さんは、乾いた不良特有の声で、ははっと笑う。
「どっちかつってんだけどー。ま、とにかくあたいはさくさく派っていうのを分かって欲しい。マックとかでさくさくのが沢山入ってると、うっしゃ!って一人喜んでるんですよ」
「まじかー」
「や、まじって思ってる?目が死んだ魚の目のように虚ろだYO ?ミス青山」
「まぁ、私はもう人生死んでっからね」
普通は、このDJ 的な口調に突っ込みを入れたところだろうが、私にはそんな気力は到底なかった。
「ま、人生死んでるかもだけど、アンタはとりま、まだ生きてんじゃん。だからさー。お悩み相談でも何でもあたいにしーよ。心軽くする程度のことなら出来ると思うから」
彼女にとっては何気ない一言だったのかも知れないが、その言葉は私の心に一つの光を灯した。
_不良でも優しい人はいるんだ。ってまだ分かんないけどね。
「考えてみる」
「なんだよー。暗いなー。ま、あたいは、週四回位なら、この芝生に来れっから。んじゃ、シーユー!」
「ば、ばいばい?」
何だかやけに疲れた。私はあくびを噛み殺す。
きっとそれは、不良と話すという、あまりに現実味のない出来事があった為だろう。
私は肩を揉みほぐすと、のろのろと立ち上がった。そうして、スウェット地の服に付いた草を手でぱらりとはらう。
_今日も、上下スウェットというださい格好で来ちゃったよ。まあ良いや、帰ろう。
私はゆっくりとした歩調で、芝生岸の舗装された道路を歩くも、全身が麻痺したかのように感覚がない。
_もしかして私って本当に死んでる?幽霊?で、麻美さんには幽霊が見えるとか…。
そんな下らないことを、私は考えてしまっていた。あり得ない。
すると、いきなり雨がぽつぽつと振りだしてきた。それはすぐに本降りに変わった。
雨は、近くにあった古びた家のトタンの屋根を強く打ち付けている。
「もー、何でこんな時に…」
私は不満を言いつつ走るも、普段走ることなどなかった為、思うように速く走れなかった。日頃の運動不足を痛感した私だった。