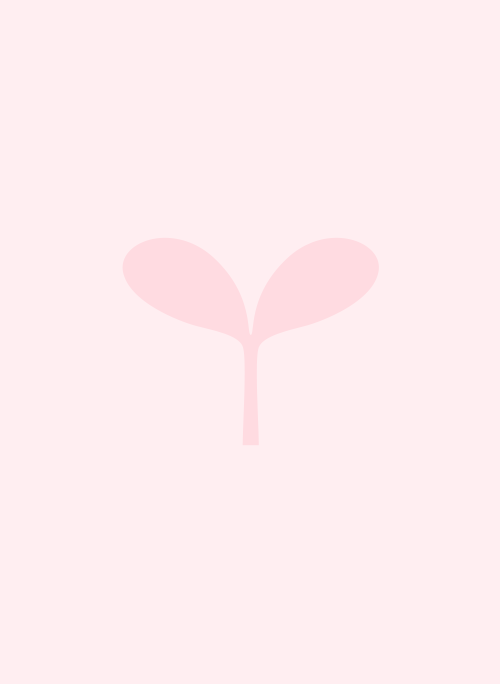と尋ねる目はやっぱり優しかった。さっきのバーの店員さんみたいに美形じゃないし、数十分前に別れたばかりなのに、言いようのない懐しさを覚えていることに気付く。
「お店に残してきた」
とわたしは傘を差したまま、見上げて答えた。
パスケースを差し出すと、ありがとう、と受け取ってから、すぐに踵を返した。
「もう、帰るの?」
とっさに呼びかけたとき、中岡さんの目に見たことのない色が映り込んだ。
「薬が家にあるから」
と彼は静かな声で言った。わたしが風邪を引いたときに、薬飲まなきゃ、と呟くのとは全く違った深刻さを伴った言い方で。くすり、という単語が聞いたこともないくらいに重く響いた。
「決まった時間にかならず飲まないと効かなくなってくるから。ほんと、ごめん」
「中岡さん」
とわたしはたまらずに呟いた。
「ねえ、もっとちゃんと話そう」
「話すって、なにを」
「教えて。色々。自分でも調べてみたけど、どうしたら感染するとか、検査までの流れとかしか分からなかったから。本当に治療して生活してる人のことは、全然」
中岡さんは苦笑して、まいったな、と漏らした。
的外れなことを言ったかと思って背中が強張る。分からないくせに踏み込みすぎたかとも。でも、そのまま傘を持っていない方の手をつながれた。初めて、強く、しっかりと。
「お店に残してきた」
とわたしは傘を差したまま、見上げて答えた。
パスケースを差し出すと、ありがとう、と受け取ってから、すぐに踵を返した。
「もう、帰るの?」
とっさに呼びかけたとき、中岡さんの目に見たことのない色が映り込んだ。
「薬が家にあるから」
と彼は静かな声で言った。わたしが風邪を引いたときに、薬飲まなきゃ、と呟くのとは全く違った深刻さを伴った言い方で。くすり、という単語が聞いたこともないくらいに重く響いた。
「決まった時間にかならず飲まないと効かなくなってくるから。ほんと、ごめん」
「中岡さん」
とわたしはたまらずに呟いた。
「ねえ、もっとちゃんと話そう」
「話すって、なにを」
「教えて。色々。自分でも調べてみたけど、どうしたら感染するとか、検査までの流れとかしか分からなかったから。本当に治療して生活してる人のことは、全然」
中岡さんは苦笑して、まいったな、と漏らした。
的外れなことを言ったかと思って背中が強張る。分からないくせに踏み込みすぎたかとも。でも、そのまま傘を持っていない方の手をつながれた。初めて、強く、しっかりと。