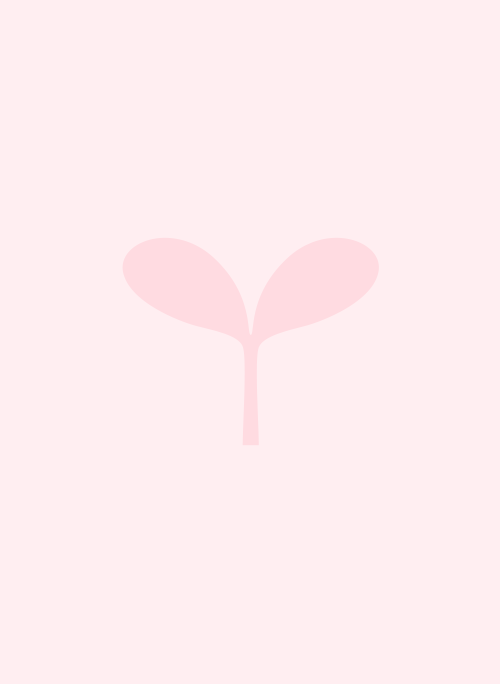「それは、災難だったね」
とだけわたしは言った。
燻製の卵にナイフを入れる。醤油と煙っぽい香りが口の中に広がると、さっきの焼き鳥屋を思い出した。中岡さんはマンションに着いた頃だろうか。
「てかさあ、けっこうな数の男が耳舐めようとするのってなんなの。あとキスマーク付けたがるやつも。高校生かっつーの。三十歳にもなって、そんなの自慢したいわけないじゃん。ビッチだと思われるだけだし」
「わたしは自慢したいけど」
みき子がぼやいた。土居ちゃんは無視して、デート相手の愚痴を延々語っていた。
わたしは目の前のグラスに口を付けた。かすかに甘い紅茶の香り。ずいぶんと上品で、いくらでもするする飲めそうだった。中岡さんはそんなことしないと思うけどなあ、と考えていたら、またもやもやとした。そんなこと分からない。知りたいようでいて、頭の片隅では怖いくらいに足がすくんでいる自分がいる。
そのとき、スマートホンが鳴った。耳に当ててびっくりする。中岡さんだった。
「ごめん、さっきの文庫本の袋の中に、僕のパスケース入ってなかったかな」
わたしは慌ててバッグの中から紺色のレジ袋を取り出した。たしかに、焦げ茶色の革のパスケースがあった。
とだけわたしは言った。
燻製の卵にナイフを入れる。醤油と煙っぽい香りが口の中に広がると、さっきの焼き鳥屋を思い出した。中岡さんはマンションに着いた頃だろうか。
「てかさあ、けっこうな数の男が耳舐めようとするのってなんなの。あとキスマーク付けたがるやつも。高校生かっつーの。三十歳にもなって、そんなの自慢したいわけないじゃん。ビッチだと思われるだけだし」
「わたしは自慢したいけど」
みき子がぼやいた。土居ちゃんは無視して、デート相手の愚痴を延々語っていた。
わたしは目の前のグラスに口を付けた。かすかに甘い紅茶の香り。ずいぶんと上品で、いくらでもするする飲めそうだった。中岡さんはそんなことしないと思うけどなあ、と考えていたら、またもやもやとした。そんなこと分からない。知りたいようでいて、頭の片隅では怖いくらいに足がすくんでいる自分がいる。
そのとき、スマートホンが鳴った。耳に当ててびっくりする。中岡さんだった。
「ごめん、さっきの文庫本の袋の中に、僕のパスケース入ってなかったかな」
わたしは慌ててバッグの中から紺色のレジ袋を取り出した。たしかに、焦げ茶色の革のパスケースがあった。