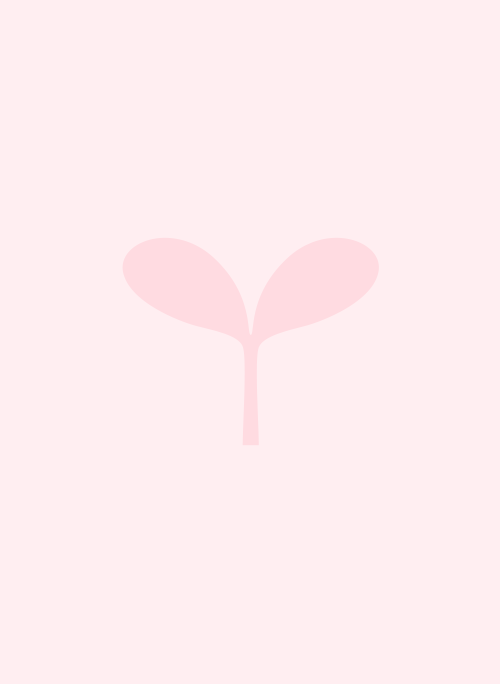「土居ちゃん、今日は仕事?」
とわたしは尋ねた。彼女はフリーのライターをしていて、女性誌で記事を書いたりしている。
「違う。デートだったんだけど、ありえないから帰って来た」
「え、なんで?」
と思わず好奇心が出てしまう。
燻製の盛り合わせです、と啓太君が愛想のない顔でお皿を出した。黒縁の眼鏡を掛けた端整な容姿にやっぱり視線がいってしまう。
一年前に初めてこの店を訪れたわたしたちは、店員の二人を見て
「店員さんの顔だけで、三ツ星レストランの満足度に匹敵しない?」
「三ツ星どころか、五ツ星だよ!」
と盛り上がり、店名がややこしいイタリア語で覚えづらかったこともあって、五ツ星という通称になったのだった。
「やっぱりこの燻製カマンベールチーズ美味しいわ」
土居ちゃんがバケットに薄く色づいたチーズを塗りながら、呟いた。
「それで?」
「会って二回目で、フレンチの店を出た途端、雨だからとか言って腰に手を回してきて。そんな気取るほどいい男でもないのに。おまけに路地に連れ込まれて、いきなりがっと」
「え?一回りも年上なのに会計が折半だったことに怒ってたんじゃないんだ」
みき子が振り向いた。
「それもあるけど、その後だよ。無理やりキスされた挙句に」
わたしたちは反射的に、きゃーっ、と女子高生みたいな声をあげたけれど
「………耳舐められた」
土居ちゃんはそう呟くと、早く忘れたいっ、とガッと頭を抱え込んだ。
とわたしは尋ねた。彼女はフリーのライターをしていて、女性誌で記事を書いたりしている。
「違う。デートだったんだけど、ありえないから帰って来た」
「え、なんで?」
と思わず好奇心が出てしまう。
燻製の盛り合わせです、と啓太君が愛想のない顔でお皿を出した。黒縁の眼鏡を掛けた端整な容姿にやっぱり視線がいってしまう。
一年前に初めてこの店を訪れたわたしたちは、店員の二人を見て
「店員さんの顔だけで、三ツ星レストランの満足度に匹敵しない?」
「三ツ星どころか、五ツ星だよ!」
と盛り上がり、店名がややこしいイタリア語で覚えづらかったこともあって、五ツ星という通称になったのだった。
「やっぱりこの燻製カマンベールチーズ美味しいわ」
土居ちゃんがバケットに薄く色づいたチーズを塗りながら、呟いた。
「それで?」
「会って二回目で、フレンチの店を出た途端、雨だからとか言って腰に手を回してきて。そんな気取るほどいい男でもないのに。おまけに路地に連れ込まれて、いきなりがっと」
「え?一回りも年上なのに会計が折半だったことに怒ってたんじゃないんだ」
みき子が振り向いた。
「それもあるけど、その後だよ。無理やりキスされた挙句に」
わたしたちは反射的に、きゃーっ、と女子高生みたいな声をあげたけれど
「………耳舐められた」
土居ちゃんはそう呟くと、早く忘れたいっ、とガッと頭を抱え込んだ。