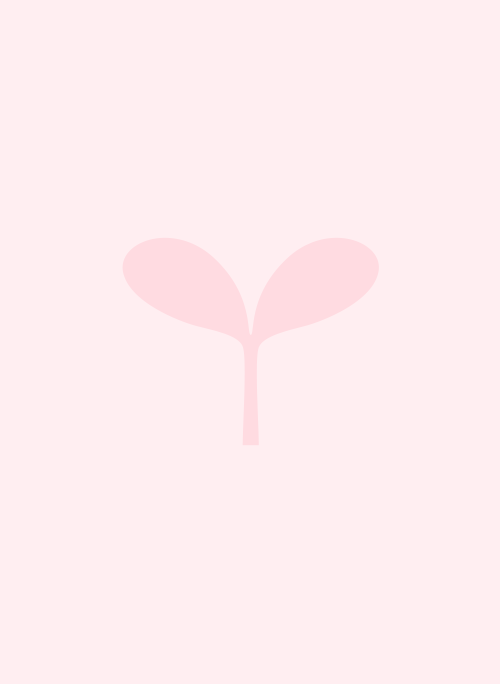その瞬間、急に緊張がこみ上げてきた。受け止め合ったことに対する動揺が生まれる。
砂浜を一緒に歩いた。好きだと言われたこと。エイズだと言われたこと。まだだいぶ混乱していた。潮風はだんだん冷たくなっていく。
「しらす、美味しかったね」
と沈んでいく日を見ながら、呟いてみた。
「うん。僕も、美味しかった」
と中岡さんは答えた。まるでわたしを気遣うように。その優しさが、さっきまでまるで違う切なさを伴って胸を締め付けた。
「本当に、また誘ってくれますか?」
そう尋ねたら、彼は遠慮がちに、うん、と頷いた。
「今度は、どこへ行こうか」
どこへ行きましょうか。
どこへ行くか。
三十歳のわたしは、その日、夕方の春の海辺で、どこへ行けるか分からない恋を始めた。
砂浜を一緒に歩いた。好きだと言われたこと。エイズだと言われたこと。まだだいぶ混乱していた。潮風はだんだん冷たくなっていく。
「しらす、美味しかったね」
と沈んでいく日を見ながら、呟いてみた。
「うん。僕も、美味しかった」
と中岡さんは答えた。まるでわたしを気遣うように。その優しさが、さっきまでまるで違う切なさを伴って胸を締め付けた。
「本当に、また誘ってくれますか?」
そう尋ねたら、彼は遠慮がちに、うん、と頷いた。
「今度は、どこへ行こうか」
どこへ行きましょうか。
どこへ行くか。
三十歳のわたしは、その日、夕方の春の海辺で、どこへ行けるか分からない恋を始めた。