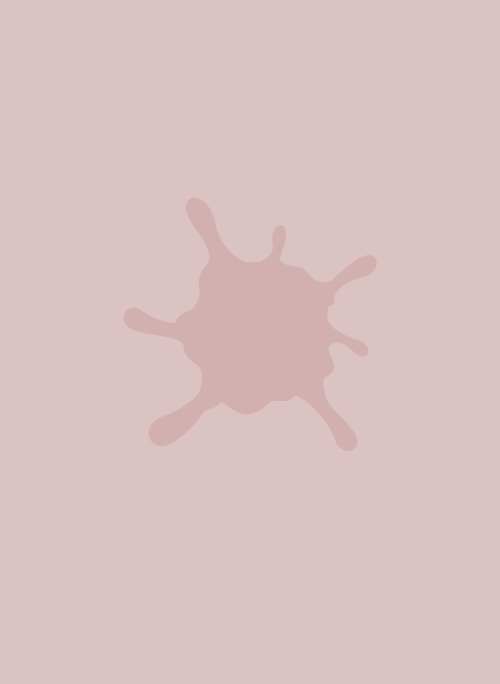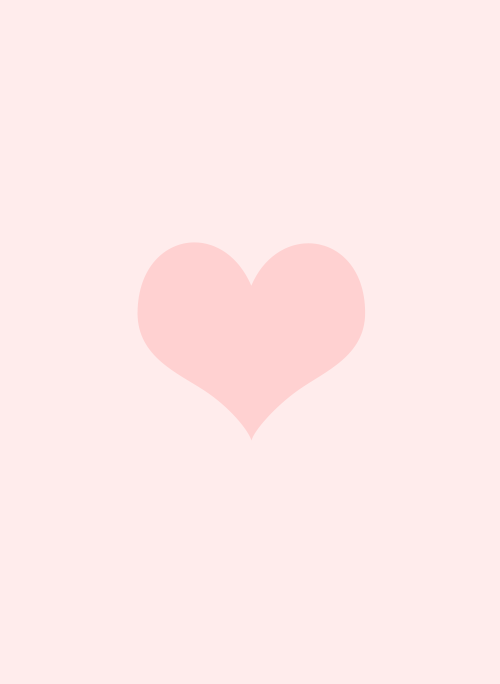ふたりだけで暮らすようになってから、人の気配に敏感になるようになった。もし、母さんがいなくなったら、パクはひとりぼっちになってしまう、そんな不安がいつも頭の中にあったからだ。
熱はいつの間にか下がっていた。体調が元に戻ると、感覚も一緒に元に戻ってきた。
―――あれ、母さん?
家の中に、違和感を覚えた。パクは以前にも、この感じに似た感覚を経験している。父親のテミロがいなくなった時だ。嫌な感覚を振り払おうと、まだ重い体を無理矢理起こした。
「母さん?」
声を出すと、喉が痛い。それでも、呼び続けた。
「母さん?母さん?」
そんなに大きくない家の中を、隅から隅まで探す。しかし、どこにも母親の姿は、見あたらなかった。
「まさか・・・。」
背中に冷たい汗が流れるのを感じた。自分の考えを、すべて否定してほしいと思いながら、一つ目の扉を開けた。
鎖がない。そこになければいけないはずの鎖が、そこにはなかった。
不安は現実になっていった。
熱はいつの間にか下がっていた。体調が元に戻ると、感覚も一緒に元に戻ってきた。
―――あれ、母さん?
家の中に、違和感を覚えた。パクは以前にも、この感じに似た感覚を経験している。父親のテミロがいなくなった時だ。嫌な感覚を振り払おうと、まだ重い体を無理矢理起こした。
「母さん?」
声を出すと、喉が痛い。それでも、呼び続けた。
「母さん?母さん?」
そんなに大きくない家の中を、隅から隅まで探す。しかし、どこにも母親の姿は、見あたらなかった。
「まさか・・・。」
背中に冷たい汗が流れるのを感じた。自分の考えを、すべて否定してほしいと思いながら、一つ目の扉を開けた。
鎖がない。そこになければいけないはずの鎖が、そこにはなかった。
不安は現実になっていった。