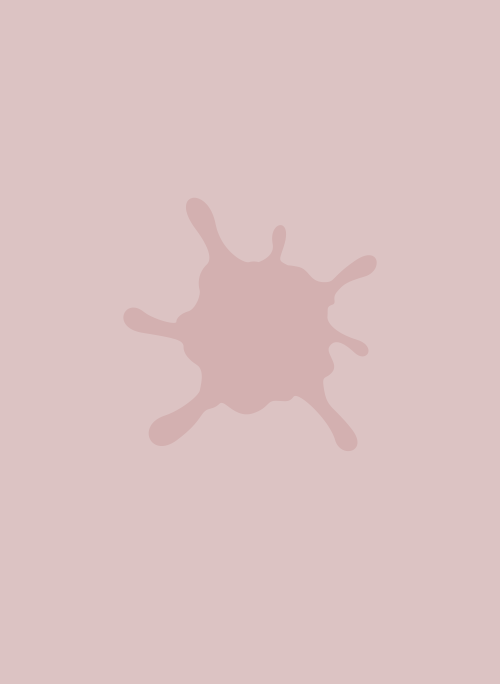「う、うん」
「じゃあ一緒に来てよ」
すっと差し出された右手を掴むとき、本物の彼女な気になってしまう。錯覚する。
大賀君に手を引かれる私に、自ずと教室中の視線が集まった。
その視線を避けるように、教室をあとにする。
もし漫画なら、そろそろいじめられていそうなポジションだ。
でも大賀君の彼女がいじめにあったなんて話は聞いたこともないし、私も今のところ実害はない。
その理由は、大賀君が彼女に対して本気じゃない、っていうシンプルなものなんだと思う。
大賀君にとって、一番の都合のいい女っていうのが、彼女の役目であって……。
はっとした。私って、まだ都合のいい女にもなれていない。あまりにお粗末な彼女。
何のために、大賀君の隣にいるんだろう?
ふと頭を過った時、遠くの空からゴロゴロ……と低い雷鳴が聞こえてきた。
大賀君は窓の外の様子を確認するように立ち止まる。
「すごい雨」
そこらじゅうの教室から、バタンバタンと勢いよく窓を閉める音が聞こえてきた。
窓を一枚閉めた大賀君の隣で、彼と同じように窓の外に目を向ける。
太い線を作る雨粒は地面を叩き、アスファルトを黒く塗りつぶしていく。
「じゃあ一緒に来てよ」
すっと差し出された右手を掴むとき、本物の彼女な気になってしまう。錯覚する。
大賀君に手を引かれる私に、自ずと教室中の視線が集まった。
その視線を避けるように、教室をあとにする。
もし漫画なら、そろそろいじめられていそうなポジションだ。
でも大賀君の彼女がいじめにあったなんて話は聞いたこともないし、私も今のところ実害はない。
その理由は、大賀君が彼女に対して本気じゃない、っていうシンプルなものなんだと思う。
大賀君にとって、一番の都合のいい女っていうのが、彼女の役目であって……。
はっとした。私って、まだ都合のいい女にもなれていない。あまりにお粗末な彼女。
何のために、大賀君の隣にいるんだろう?
ふと頭を過った時、遠くの空からゴロゴロ……と低い雷鳴が聞こえてきた。
大賀君は窓の外の様子を確認するように立ち止まる。
「すごい雨」
そこらじゅうの教室から、バタンバタンと勢いよく窓を閉める音が聞こえてきた。
窓を一枚閉めた大賀君の隣で、彼と同じように窓の外に目を向ける。
太い線を作る雨粒は地面を叩き、アスファルトを黒く塗りつぶしていく。