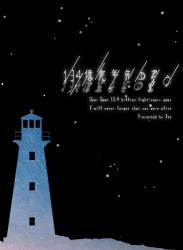髪を退かそうとして耳に触れた三神くんの中指に、私は悲鳴にも似た声を上げた。
早鐘を打つ心臓は、まるで全身を飲み込んでしまったみたいだ。
耳にも、指先にも、体の奥にも、どくどくと血が巡る。
多分、顔は真っ赤。
「いや、そんな驚かんでも」
三神くんは耳に指を突っ込みながら、呆れたように言うけれど、私はそれどころじゃなかった。
最近、ずっとそう。
三神くんが近づくと、心臓がおかしくなる。
鼓動が暴れて、自分じゃどうにもできなくて。
私が私じゃないみたいだ。
なのに三神くんはこっちの気も知らないで。
「み」
「み?」
「三神くんの馬鹿!」
「あ?」
「もう知りません!」
思いっきり顔を顰めた三神くんを放って、私はぴゃーっとその場から逃走する。
完全に言い逃げだ。
体調だけが気掛かりだったけれど、顔色はもう元に戻っていたから問題は無いだろう。
足取りもしっかりしていた。
置いていかれた三神くんは怪訝な顔をしていたけれど、そもそも勝手に触る三神くんが悪いんだ。
腕や手はまだしも、髪とか耳とか、三神くんは時々距離感がおかしい。
本人は自覚していないんだろうか。
誰にでもそう?
三神くんはお姉さんがいるらしいから、それでかもしれない。
でも──
「やっぱり、調子が狂う」
詰めた息の合間に呟いた言葉は、風の音に紛れて消える。
近づいて欲しいような、欲しくないような。
そんな気持ちを、私は持て余していた。
早鐘を打つ心臓は、まるで全身を飲み込んでしまったみたいだ。
耳にも、指先にも、体の奥にも、どくどくと血が巡る。
多分、顔は真っ赤。
「いや、そんな驚かんでも」
三神くんは耳に指を突っ込みながら、呆れたように言うけれど、私はそれどころじゃなかった。
最近、ずっとそう。
三神くんが近づくと、心臓がおかしくなる。
鼓動が暴れて、自分じゃどうにもできなくて。
私が私じゃないみたいだ。
なのに三神くんはこっちの気も知らないで。
「み」
「み?」
「三神くんの馬鹿!」
「あ?」
「もう知りません!」
思いっきり顔を顰めた三神くんを放って、私はぴゃーっとその場から逃走する。
完全に言い逃げだ。
体調だけが気掛かりだったけれど、顔色はもう元に戻っていたから問題は無いだろう。
足取りもしっかりしていた。
置いていかれた三神くんは怪訝な顔をしていたけれど、そもそも勝手に触る三神くんが悪いんだ。
腕や手はまだしも、髪とか耳とか、三神くんは時々距離感がおかしい。
本人は自覚していないんだろうか。
誰にでもそう?
三神くんはお姉さんがいるらしいから、それでかもしれない。
でも──
「やっぱり、調子が狂う」
詰めた息の合間に呟いた言葉は、風の音に紛れて消える。
近づいて欲しいような、欲しくないような。
そんな気持ちを、私は持て余していた。