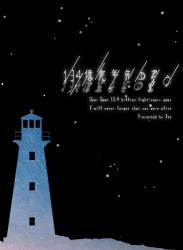*
じりじりと鋭い陽射しが肌を焼く。
耳を打つ波の音はどこか遠く、巻き戻ることのない時間が私と慧くんの間に沈黙を落とす。
なにから話せばいいのか。
なにを話せばいいのか。
罪悪感が喉につっかえて、何度も言葉を紡ぐのに逡巡する。
慧くんはその罪悪感すら、知る由もないのに。
だから、最初に口を開いたのは慧くんだった。
「……大丈夫? なんもされてない?」
「あ……うん。慧くんが助けてくれたから。ありがとう」
あの時、慧くんが腕を引いてくれなかったら、危なかった。
今更ながら恐怖を感じて片腕を抱く。
指先に触れる温度は、じっとりと汗をかいているのにかすかに冷たい。
「よかった、間に合って。……すぐ分かった。髪も伸びてんのに、なんでかな」
そう言って照れたみたいに笑う慧くんは、記憶の中よりもずっと背が伸びていた。
顎のラインは直線的に、いつも少し掠れていた声は穏やかなテノールを奏でるようになり、もう“慧くん”なんて、甘く子どもっぽい呼び方をしてはいけないような、そんな気さえする。
2年という月日は、慧くんを少年から青年にするには十分な時間だった。
「未琴も遊びに来たの?」
「うん。友達が誘ってくれたんです」
「そっか、友達。俺も──友達と」
私たちの間で“友達”という言葉は特別な意味を持つ。
互いに互いしかいなかったあの頃、私は慧くんの他に友達と呼べるような人ができるなんて想像すらしていなかった。
きっと、慧くんも同じだったはずだ。
それが今は、それぞれに友達だと思える人がいて、離れていたこの2年の間が無意味なものではなかったのだと、少しだけ愛おしく感じる。
立ち止まっていたにせよ、きちんと時間は流れていた。
じりじりと鋭い陽射しが肌を焼く。
耳を打つ波の音はどこか遠く、巻き戻ることのない時間が私と慧くんの間に沈黙を落とす。
なにから話せばいいのか。
なにを話せばいいのか。
罪悪感が喉につっかえて、何度も言葉を紡ぐのに逡巡する。
慧くんはその罪悪感すら、知る由もないのに。
だから、最初に口を開いたのは慧くんだった。
「……大丈夫? なんもされてない?」
「あ……うん。慧くんが助けてくれたから。ありがとう」
あの時、慧くんが腕を引いてくれなかったら、危なかった。
今更ながら恐怖を感じて片腕を抱く。
指先に触れる温度は、じっとりと汗をかいているのにかすかに冷たい。
「よかった、間に合って。……すぐ分かった。髪も伸びてんのに、なんでかな」
そう言って照れたみたいに笑う慧くんは、記憶の中よりもずっと背が伸びていた。
顎のラインは直線的に、いつも少し掠れていた声は穏やかなテノールを奏でるようになり、もう“慧くん”なんて、甘く子どもっぽい呼び方をしてはいけないような、そんな気さえする。
2年という月日は、慧くんを少年から青年にするには十分な時間だった。
「未琴も遊びに来たの?」
「うん。友達が誘ってくれたんです」
「そっか、友達。俺も──友達と」
私たちの間で“友達”という言葉は特別な意味を持つ。
互いに互いしかいなかったあの頃、私は慧くんの他に友達と呼べるような人ができるなんて想像すらしていなかった。
きっと、慧くんも同じだったはずだ。
それが今は、それぞれに友達だと思える人がいて、離れていたこの2年の間が無意味なものではなかったのだと、少しだけ愛おしく感じる。
立ち止まっていたにせよ、きちんと時間は流れていた。