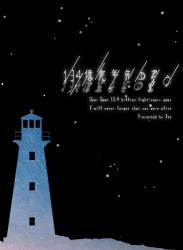『俺さ、気付いたんだ。“誰か”をやってみたって俺は結局“誰か”にはなれないし、俺が“誰か”を辞めたところで世界は滅亡なんかしない。
ずっと“誰か”を生きてたら、俺はいつ自分の命を自分と自分の大切な人のために使うんだろう。寿命は限られてんのにって』
慧くんは眉を下げ、どこまでも優しく、寂しく、泣き出しそうな顔で笑った。
『未琴、俺はこうして、大切な人と過ごす何でもない日常に、自分の命を使いたいって思ったんだ』
慧くんがそう言った瞬間、見開いた目の縁から、透明な雫が零れていくのを感じた。
教室は途方もなく暑いのに涙はもっと熱く、頬を伝って顎の先から滑り落ちる。
一粒の雫を受けたプリーツスカートが、その場所だけ濃紺に色付いた。
意味もなく苦しくて、切なくて、これがどんな感情からくるものなのか、私には分からなかった。
『未琴』
慧くんがまた私の名前を呼ぶ。
慧くんが変わってしまっても、その呼び方だけは変わらなかった。
『未琴が未琴でいても、誰も文句なんて言わない』
『……私が、私でいても』
パァー、と吹奏楽部のチューニングの音が、訪れた沈黙の隙間を埋める。
それが鳴り止むと同時に、横に揺れた髪が頬を撫でた。
視界の端には、吹き込んだ風にあたってパタパタとはためく古典のプリントの束があった。
ずっと“誰か”を生きてたら、俺はいつ自分の命を自分と自分の大切な人のために使うんだろう。寿命は限られてんのにって』
慧くんは眉を下げ、どこまでも優しく、寂しく、泣き出しそうな顔で笑った。
『未琴、俺はこうして、大切な人と過ごす何でもない日常に、自分の命を使いたいって思ったんだ』
慧くんがそう言った瞬間、見開いた目の縁から、透明な雫が零れていくのを感じた。
教室は途方もなく暑いのに涙はもっと熱く、頬を伝って顎の先から滑り落ちる。
一粒の雫を受けたプリーツスカートが、その場所だけ濃紺に色付いた。
意味もなく苦しくて、切なくて、これがどんな感情からくるものなのか、私には分からなかった。
『未琴』
慧くんがまた私の名前を呼ぶ。
慧くんが変わってしまっても、その呼び方だけは変わらなかった。
『未琴が未琴でいても、誰も文句なんて言わない』
『……私が、私でいても』
パァー、と吹奏楽部のチューニングの音が、訪れた沈黙の隙間を埋める。
それが鳴り止むと同時に、横に揺れた髪が頬を撫でた。
視界の端には、吹き込んだ風にあたってパタパタとはためく古典のプリントの束があった。