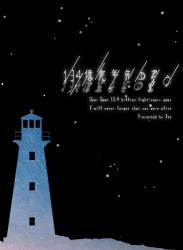*
『未琴は他人の人生を生きてるみたいだ』
中学3年の夏。
その年は教室の冷房が壊れて、身体の水分が全てなくなってしまうのではないかと思うほど暑い夏だった。
先生から通りすがりに頼まれ、ぱちん、ぱちんとプリントを留める私に、彼──慧くんがぽつりと漏らした言葉を、私はまだ、映画のように鮮明に思い出すことができる。
まるで自分のことかのように悔しそうに、もどかしそうに微かな怒りを顕にした慧くんは、あの夏、私を解放してくれた唯一の人だった。
クラスは違った。
同じ小学校の知り合いでもない。
ただ、彼もまた、私と同じように“誰か”を引き受けてしまうような、お人好しだっただけ。
任意出席のクラス委員招集に真面目に出席した、たった二人の私たちは、その前の年、中学2年の冬に出会った。
『皆、来てると思った』
『誰も来ないね』
『俺たちだけでやるのかな』
『そうじゃなければいいんだけど』
『未琴は他人の人生を生きてるみたいだ』
中学3年の夏。
その年は教室の冷房が壊れて、身体の水分が全てなくなってしまうのではないかと思うほど暑い夏だった。
先生から通りすがりに頼まれ、ぱちん、ぱちんとプリントを留める私に、彼──慧くんがぽつりと漏らした言葉を、私はまだ、映画のように鮮明に思い出すことができる。
まるで自分のことかのように悔しそうに、もどかしそうに微かな怒りを顕にした慧くんは、あの夏、私を解放してくれた唯一の人だった。
クラスは違った。
同じ小学校の知り合いでもない。
ただ、彼もまた、私と同じように“誰か”を引き受けてしまうような、お人好しだっただけ。
任意出席のクラス委員招集に真面目に出席した、たった二人の私たちは、その前の年、中学2年の冬に出会った。
『皆、来てると思った』
『誰も来ないね』
『俺たちだけでやるのかな』
『そうじゃなければいいんだけど』