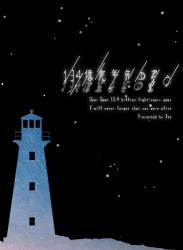「……かき氷、食べませんか?ほら、三神くんの手の近く、溶け始めてる」
少しでも空気を軽くしたくて、私は三神くんの顔を覗き込んだ。
せっかくのかき氷だ。
ドロドロになってしまう前に堪能しなければもったいない。
考えても仕方のないことは置いておいて、この瞬間を楽しむが吉だ。
私はストローのスプーンで氷の山を崩し、シロップをたっぷりと含んだ雪を口に運ぶ。
氷の痺れるような冷たさとともに、甘酸っぱいあんずの風味が口の中に広がって、私は思わずカップを持っていない方の手で口元を押えた。
「美味しい……これ、当たりですよ三神くん……!」
爽やかな香りはまるで夏そのもののようで、三神くんに感動を共有したくなる。
心を動かされるどんなことも、三神くんとならもっと色鮮やかになることを私は知っていた。
そっと、三神くんを窺う。
三神くんは目が合うと観念したように微かに笑った。
そして大きな手をストローを持つ私の右手に伸ばし、ぐっと引き寄せる。
「あっ!」
「うま」
近くなった端正な顔が離れていく。
少し低い体温が触れたのは一瞬で、それでも重なった指先からぶわりと熱が広がった。
少しでも空気を軽くしたくて、私は三神くんの顔を覗き込んだ。
せっかくのかき氷だ。
ドロドロになってしまう前に堪能しなければもったいない。
考えても仕方のないことは置いておいて、この瞬間を楽しむが吉だ。
私はストローのスプーンで氷の山を崩し、シロップをたっぷりと含んだ雪を口に運ぶ。
氷の痺れるような冷たさとともに、甘酸っぱいあんずの風味が口の中に広がって、私は思わずカップを持っていない方の手で口元を押えた。
「美味しい……これ、当たりですよ三神くん……!」
爽やかな香りはまるで夏そのもののようで、三神くんに感動を共有したくなる。
心を動かされるどんなことも、三神くんとならもっと色鮮やかになることを私は知っていた。
そっと、三神くんを窺う。
三神くんは目が合うと観念したように微かに笑った。
そして大きな手をストローを持つ私の右手に伸ばし、ぐっと引き寄せる。
「あっ!」
「うま」
近くなった端正な顔が離れていく。
少し低い体温が触れたのは一瞬で、それでも重なった指先からぶわりと熱が広がった。