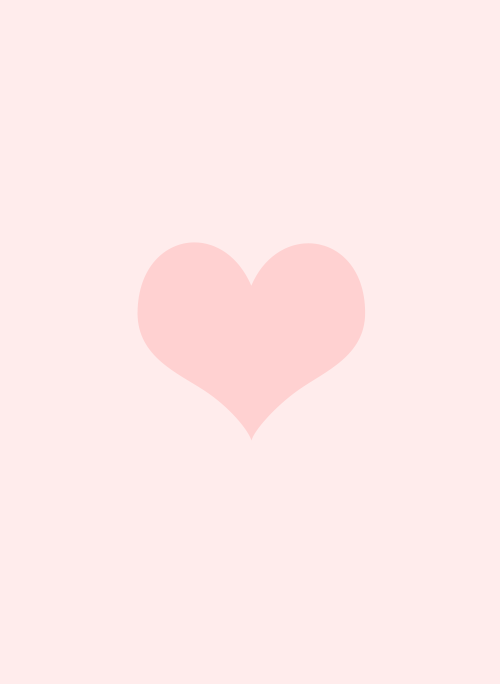扉を押し開き外の空気に触れてしまえば更に確信する魔女の匂い。
そう遠くない距離に魔女がいる。
いつも以上に研ぎ澄まされている狼の血がその方向までも見定め教えてくるのだ。
行くか?
なんて、血が滾ったのは一瞬。
次の瞬間には背後から服をキュッと掴まれ遠くを見つめていた意識が引き戻され。
そのまま振り返れば澄んだ水色の双眸に見つめ上げられ高ぶりの鎮静。
「あ……」
そうだ。
そうだった。
今日は非番で、今は六花とデートの最中で。
一瞬六花の存在すらも忘れて仕事モードに突っ走ってしまった。
デート中にあるまじき失態に我に返ってしまえば一気に血の気が引くのも仕方のない事。
そんなソルトの動揺に六花のまっすぐな眼差しは、どうにも咎められている様に感じてならないのだ。
六花としては咎めるなんて感情とは程遠く、ただ『どうしたの?』と問いかけているに過ぎないのだが。
それでもソルトからすれば一瞬でも六花を蔑ろにしてしまったような罪悪感からの気まずさのマックス。
とにかく何かフォローをとただただ可笑しな笑顔で六花を見下ろしていた最中。
タイミングよく鳴り出したのはソルトの携帯。
当然天の助けとばかりに『あ、電話だ』なんて気まずさから逃げるように携帯に手を伸ばしたのだが、表示されている【蓮華】の文字には嫌な予感しか浮上しない。