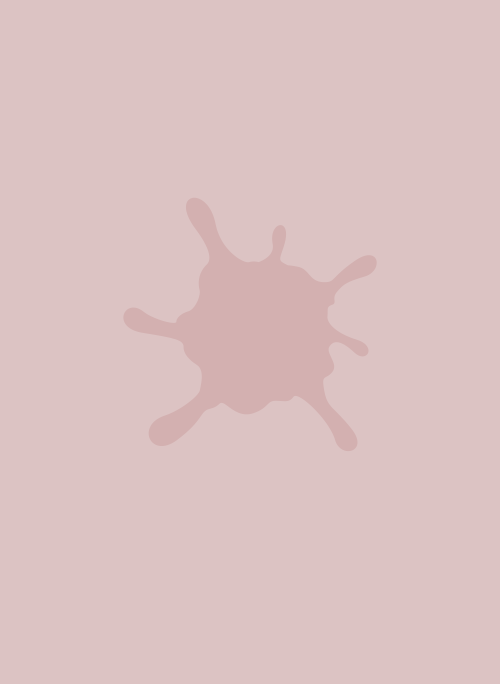「オマエに
拒否権なんかないんだよ」
悪魔が笑いながら言った。
足で頭を踏みつけられ
顔を床に打ち付ける。
「暫くそうしてな」
痛みに、視界が揺らいだ。
「やめ…て」
「オマエは私の為に働けばいい。
…あぁ、私に逆らおうなんて
考えるんじゃないよ?」
女の白く痩せ細った手が、
私のカバンに伸びるのが見えた。
やめて……。
もう声が出ない。
「私の後ろに誰がいるか、
わかってるんだろ?
逆らったら…命はない。
わかってるだろうね?」
あぁ、そっか。
だからこの女は今日
わざわざここに来たんだ。
私は唇をかみしめる。
口の中は、血の味で満ちていた。
「…わかってるならそれでいい。
明日からもちゃんと働くんだよ」