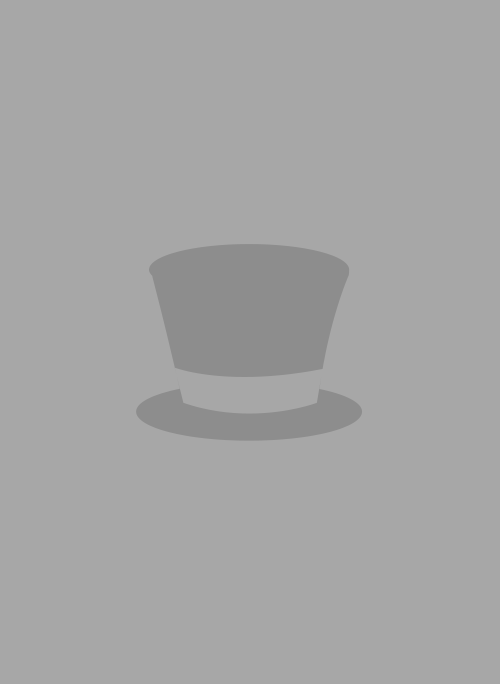「里枝(さとえ)、今日も遅くなるの?」
「うん、まぁ」
「夕飯までに帰ってくる?」
「わかんない。あたしの分は作らなくていいから。由梨(ゆり)もそのほうが楽でしょ」
「…わかった」
背中で聞く由梨の声は、吐息のように静かだった。
「いってくる」
「うん、いってらっしゃい」
あたしはパンプスを素早く履いて、由梨の顔も見ずに部屋を出た。
空は重い雲に覆われて灰色だ。私の身体も、巨大な何かに押しつぶされているように重い。
由梨の静かに私を見送る声が、耳の奥にこびりついている。あの調子の声を聞くたびに、私は無性に気分が悪くなる。いらいらする、とか、気持ち悪い、とか、そういうわかりやすい感情じゃない。もっと自分主義で、個人的な狭い感情な気がした。もう何ヶ月も、私はこの気持ちを問い続けていた。