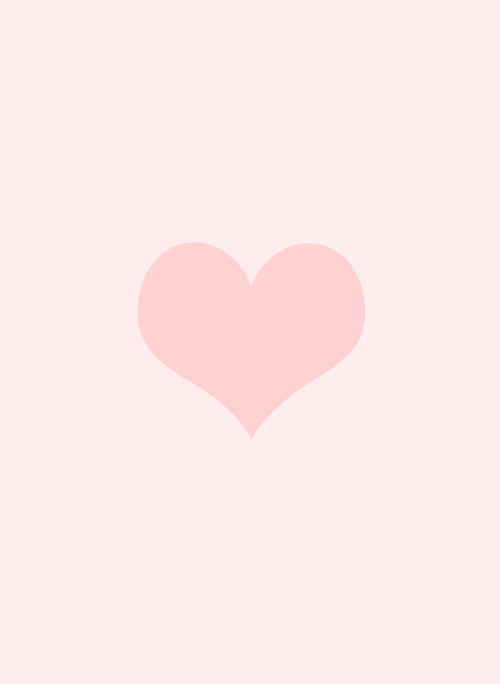「………悪い。………あいつにされた事、思い出したくない、よな。………焦って、悪かった。俺が消せるわけないのに、な。」
悔しげにそう言うと、ミツキはベットから体を下ろそうとした。
それを見て、エルハムは咄嗟にミツキの体に抱きついていた。
離れて欲しくなかった。ミツキを感じていたかった。
やっと、気持ちが繋がったのだ。
ミツキに触れて欲しいと願ってしまっている自分が居るのに、エルハムは気づいたのだ。
「………エルハム?」
「……………消せるよ。ミツキに触ってもらったら、嫌な気持ちも、幸せな思い出に変わると思う。だから、触って欲しい………。」
「…………いいのか?」
エルハムはコクンと頷くと、ゆっくりと自分の服の前ボタンをはずし服をはだけさせた。そこからは白い素肌が見え、鎖骨付近や胸には赤い跡や、歯形がくっくりと残っていた。
恥ずかしさよりも、怖さがあった。
こんな汚くない体を見て、ミツキが喜ぶはずなどないのに。
ミツキの方を見れずに俯いていると、ミツキが鎖骨のキスマークに指を置いた。
その指は先ほどキスをした唇よりも熱を持っているようだった。
「エルハムの体………綺麗だな。」
「……っっ…………。」
「俺のものになったなんて、信じられないな。」
そういうと、ミツキは嬉しそうに微笑むと、キスマークに唇を付け、ペロリの舐めた。
ぬるりとした感触。冷たさを感じるのは一瞬で、舐められた場所はすぐに熱くなり、「もう1回舐めて欲しい。」と、ねだるようだった。
その後も、ミツキはなんどもキスマークや噛み跡を舐めたり、触れたりし続けた。
「………っ………ぁ………ミツキ………。」
「こんな傷に怯えなくていい。こんなものすぐに消える。それに、残ったとしても俺はおまえが綺麗だと思うし、愛しく思うよ。」
「ありがとう………、ミツキ。」
「愛してる、エルハム。」
「…………私も、愛してる。ミツキ…………。」
キスをして、抱き締め合う。
恋人がする、そんな幸せな行為を自分も愛しい人としているのが信じられられなかった。
けれど、ミツキから受ける体温や気持ち良さ、胸が高鳴る愛の言葉。
それら全てが真実なのだと教えてくれる。
甘い吐息と水音と、2人の名前。
それが何度も繰り返させる、ゆっくりとした時間。
エルハムは、その幸せに浸りながら、何度もミツキの名前を呼び続けた。