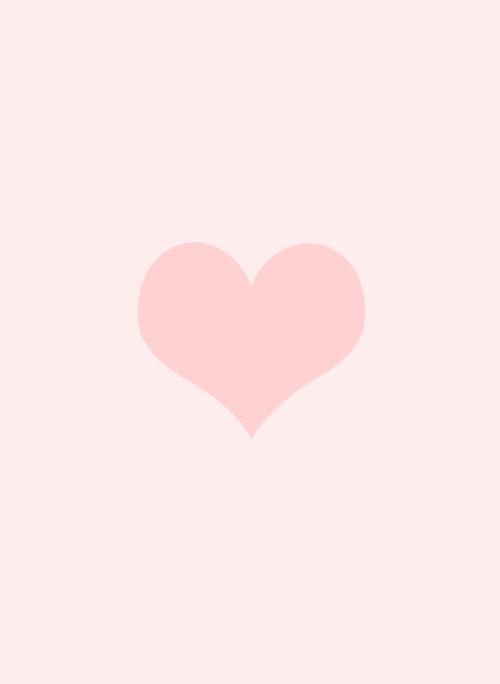「ミツキ……私はおまえを信じている。我が娘が信じた男なのだからな。この牢に入れたのも私の体裁を取りつくろうために同然だ。申し訳ない。」
「アオレン王、何を言っているのですか!?ミツキは密偵ではないですか!証拠もちゃんとあります!」
「セリムっ!おまえは、あんなものが証拠だと言えないとわかっているだろう。エルハムも言っていた通り、あの字はミツキのものではないのはわかっているはずだ。私が、ここにミツキを閉じ込めたのは、真実を知るため、そして、皆が取り合えずは安心できるためだ。……一人を犠牲にしてやる事ではなかったのだ。」
アオレン王が大声を出すことは珍しかった。
セリムに対しても、親身で優しい王であったため、セリムは驚き、そして萎縮してしまった。
けれど、アオレンが話したことは彼にとって全て心当たりのあるものばかりで反論など出来るはずもなかった。
「アオレン王………。」
「ミツキ、本当にすまなかった。お詫びならエルハムが戻ってきてから必ずしよう。………そして、教えてくれないか。エルハムがここに来た理由を。エルハムはどこに行ったのかを。」
そういうと、アオレン王はミツキの目の前で頭を下げた。そして、まっくずとミツキの瞳を見つめ返事を待っていた。
アオレン王の言葉は本当の物だとミツキは思った。
1人の王が、牢屋に入り罪人に頭を下げる王がいるだろうか。
確かにアオレン王は体裁を大切にしてしまったのかもしれない。けれど、沢山の人を纏めるためには、その体裁を取るのも必要だとミツキは理解していた。
けれど、自分が苦痛は大きかった。そして、1度嘘だとしても牢に入ったことで、ミツキを疑いの目で見てしまう人もいるだろう。
それを思うと、悔しくて仕方がなかった。
しかし、ミツキはスボンのポケットに手入れれて、先ほどいれた紙に触れた。
エルハムが書いた手紙だ。
そへに触れているだけで、ミツキは不思議と気持ちが落ち着いた。
今、ここで王の言葉に返事をしなければ、牢屋を出れたとしても、エルハムを守る時に頼れるものが少なくなるはずだ。
頼れるものには頼って、エルハムを確実に安全に見つけ出したかった。
そのためには、アオレン王の助けが必要だと考えたのだ。
ミツキは、アオレン王を黒い瞳で見つめ返した。その視線は強い決意が込められた、鋭いものだった。