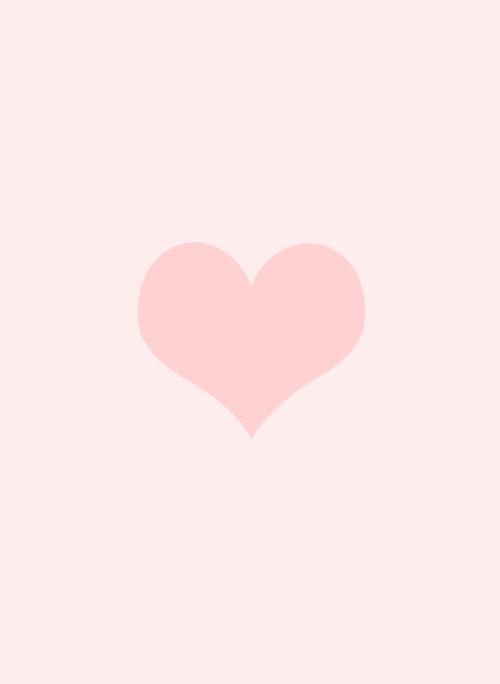そんな中、エルハムは倒れたセリムを見つめていた。生まれたときから近くにいた彼が、自分の前で倒れている。いつも優しくて守ってくれていた彼がとても辛そうにしている。
彼が怪我をするのなどわかっていたはずなのに、いざ本当に傷を負ってしまうと、エルハムは激しく動揺してしまう。
覚悟が足りないとは思う。けれど、やはり悲しくなってしまうのだ。
そのため、セリムが自室のベットに運ばれてから、エルハムは彼の傍から離れなかった。
医者にも治療して貰い、傷の手当てはしてもらった。酷い傷に見えたけれど、命の心配はないとの事だった。
けれど傷口の事もあり、しばらくの間は安静にしていなければいけないとも言われたのだった。
「…………エルハム様…………?」
「あ、セリム!気がついたのね。大丈夫?傷は平気?」
「エルハム様。ご心配かけてしまい、すみませんでした。傷の痛みは大丈夫です。………あの時はもっと早くに気づけばこんな事にはなっていなかったのに。申し訳ございません。」
「セリムは私の事を守ってくれたのよ。そんな事言わないで。」
「…………ありがとうございます。エルハム様、よろしければ夜の奇襲についてわかった事を教えていただけませんか?」
「えぇ………。」