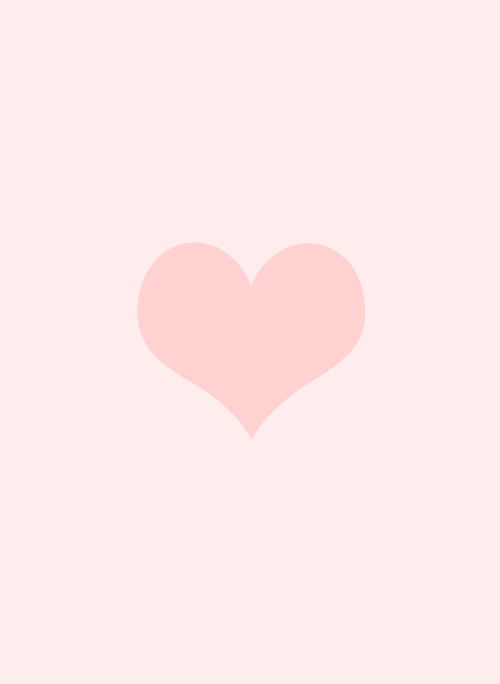『敬子のお見舞いに行ってくれない?』
それが、お母さんの「お願い」だった。
敬子というのは、お母さんの妹―つまり、あたしから見れば『叔母』にあたる人。
少し体調を崩し、先月から入院している。
あたしは敬子おばさんが苦手(絶対嫌われてる)で、正直あまり行きたくないのだけれど、
『今日行くって言っちゃってるからさ、これ渡してきてほしいのよ。』と困り顔で雑誌の束を押し付けられては、行かないわけにもいかないだろう。
すぐ帰ればいいんだし、と自分を納得させたあたしは今、大きな紙袋を持って駅前のバスロータリーに立っている。
病院まではバスで40分ぐらい。
普段使わないから知らなかったけど、その路線は本数が少ないらしく、バスが来るまで まだ20分ほどあった。
重い荷物を抱えて歩きまわる元気もないあたしは隅のほうに立つ。
ベンチに座ったおじさんは新聞を読んでいて、あたしには気づく素振りもない。
…こんなとき、少女マンガの世界なら、どこからともなく王子様みたいな人が現れて、『俺が持つよ』なんて言ってくれるんだろうな、なんてバカなことを思った。
そんな都合のいい話、あるわけないよね。
紙袋の紐が手に食い込んで痛いから、と胸に抱えてみると少しだけラクになったけれど。
それも最初だけで、だんだんと手が痛くなってくる。
重い。
痛い。
…でも、紙袋が汚れてたら、敬子おばさんはいい顔をしないだろうな、なんて考えると、下に置くこともできなくて。
もう限界かも…なんて思い始めたころ、『王子様』は現れた。
「!?」
――突然のことに、体が動かない。
後ろから抱き締めるように現れた『彼』は、片手であたしの両目を塞ぎ、もう片方の手であたしの紙袋を支えた。
普通なら、叫んで、暴れてもおかしくないほど怖い状況。
だけど、あたしは『恐怖』を感じてはいなかった。
声が出なかったのも、体が動かなかったのも。
「せ…んぱい?」
あたしを包んでいたのが、あの香りだったから。