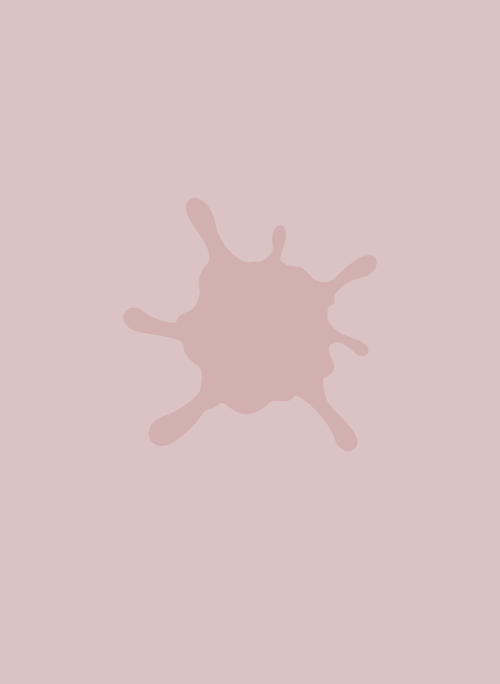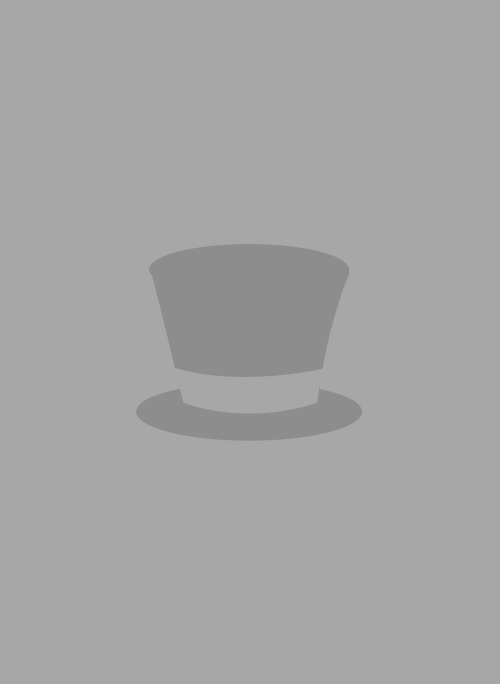その日も彼女はいつもと変わらなかった。
美しく、しなやかで、いい匂いがし、少しイカレていた。
その日も二人は抱き合っていた。
それで二人は十分に幸せだった。
ただ、頭の後ろにある妙に冷たく醒めた部分で、ずるずるとどうしようもない暗い穴にゆっくりとはまっていく感覚を覚えていた。
金はなくなりかけていた。
仕事はもう一週間も無断で休んでいた。
それでも彼女のそばを離れる気はなかった。
彼女の曇りのない目がいたずらっぽく笑った。
「少し怖いのね」
「怖くなんかないさ」
強がりだった。
このままではやがて二人は確実に破滅するだろう。
それは何よりも怖かった。
「あたしは怖いわ」
そういうと彼女は目を伏せて、胸に顔を押しつけてきた。
彼女の頭を撫でながら、泣きたくなった。
終わりは、確実に、すぐ後ろまできていた。
すると彼女はぴょこんと顔を上げ、悲しげに言った。
美しく、しなやかで、いい匂いがし、少しイカレていた。
その日も二人は抱き合っていた。
それで二人は十分に幸せだった。
ただ、頭の後ろにある妙に冷たく醒めた部分で、ずるずるとどうしようもない暗い穴にゆっくりとはまっていく感覚を覚えていた。
金はなくなりかけていた。
仕事はもう一週間も無断で休んでいた。
それでも彼女のそばを離れる気はなかった。
彼女の曇りのない目がいたずらっぽく笑った。
「少し怖いのね」
「怖くなんかないさ」
強がりだった。
このままではやがて二人は確実に破滅するだろう。
それは何よりも怖かった。
「あたしは怖いわ」
そういうと彼女は目を伏せて、胸に顔を押しつけてきた。
彼女の頭を撫でながら、泣きたくなった。
終わりは、確実に、すぐ後ろまできていた。
すると彼女はぴょこんと顔を上げ、悲しげに言った。