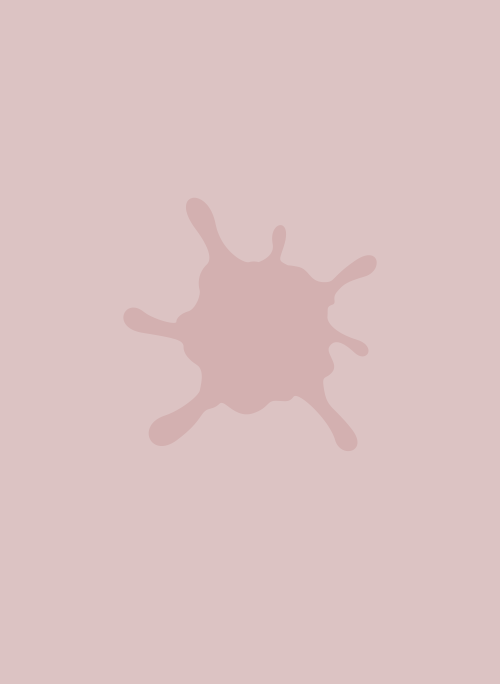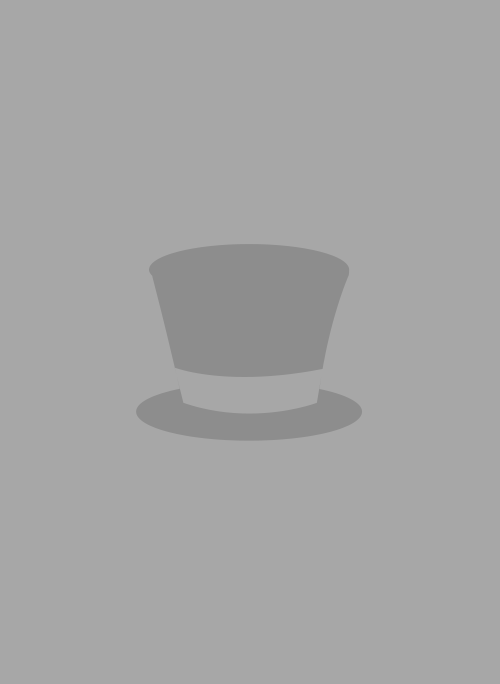翌日も、翌々日も。
沙奈と過ごす幸せな日々は、
時間は、緩やかに流れていく。
「……ねえ、沙奈」
「……なに?」
「……もしも僕が手錠を外して、足の縄を切って、目隠しを取ったら……」
沙奈の寝転ぶベッドのふちに座り、僕は彼女に問いかけた。
「君は、僕から逃げる?」
沙奈に問いを投げかけるけど、一向に答えは返ってこない。
僕は落ち着いた口調で、もう一度問う。
「……もし拘束を外したら、君は僕から逃げていく?」
「……逃げない」
その言葉に僕は沙奈の顔を見据える。
彼女の唇はなおも、言葉を形作った。
「逃げないって約束する。そう言ったら、この手錠を外してくれるの?」
「……どうだろう。多分外さない、と思う」
「……信じてくれないの?」
沙奈の声が、鋭く僕の胸を突いた。
できることなら沙奈を信じたいけれど、でも。
それでも。
「……まだ無理だよ。愛することと信じることは似ているようで違うから。君は現に、彼氏が好きだったのに、否定する彼の浮気を信じただろう」
愛しているから信じる、なんて公式は簡単には成り立たないものだから。
そうだ。
――チアキのときだって、そうだった。
「……僕が沙奈のことを信じられるようになったら外してあげるよ。僕だってずっと拘束しておくのは嫌だから」
沙奈が一度、故意か偶然か、手錠の鎖が擦れる耳障りな金属音を鳴らした。
時計を見上げた僕は夕食からかなりの時間が経過していたことに気づき、腰を上げた。
そういえば、もう夜だな。