ピンポーン。まるなが編集所のインターホンが鳴った。
時刻はもうすぐ夜7時。ここまるなが編集所には、退勤時刻はない。
編集作業・取材記事の段取りなど各々が納得するまで夜遅くまで仕事を
進めていく。
「東京山手銀行の村田ですが。」
村田は東京山手銀行の頭取を務める。そしてここの出版する月刊誌ならびに
刊行物のファンであり時々こうやって編集長を訪ねる。
「あら、いつも足を運んでくださり申し訳ないです。あ、れいの用件で
お見えになられたのですね。どうぞお入りください。」
まるなが編集所の編集長、名前は福田紀子という。「きこさん」の愛称で
古くからの取引先からはそう呼び、親しみをもたれている。おっとり、ゆったり
落ち着きある性格のアラフィフの女性だ。
「こないだは村田家所有の島に行ってきなさいだなんて 唐突なこといって
すまんかった。ハハ。」
村田は、豪農の一家の長男として生まれた。幼いころから英数塾に通わせて
もらったり、ピアノを買ってもらったりした。お金で苦労はあまりなかった。
地元のエリート進学校を出て、東京大学に一発合格。進級するにつれ頼りになる
後輩が増え、その人脈が今でも生き現在も大手金融機関で支えている者が多くい
る。
ピリリリイ...村田の携帯電話が鳴る。ほぼ毎日ではないが夜に7時8時
ごろになると愛娘ミワから電話がかかってくる。着信通知を見ずにミワと分かる。
親の勘で。
「パパ、パパ、今どこにいるですか?パパ」
娘ミワは、関西の一流大学を卒業後、東京山手銀行の主要取引先の商社に勤めている。入社2年目ではあるが、現在はハナブサ商事の副社長のとなりで渉外の補佐役を務めたり新入社員のサワコの指導に当たったりと日々忙しくもある。
「おう ミワか。今日もごくろうさん。うむ、ミワ、ごめんね、取引先の
方と一緒でさ、今日は。ごめんね。ごめん。」
ミワは、一人っ子で愛情を十分にかけられ育ち、数え切れないほどのわがままを
村田に言ってそして甘えてきた。村田の愛ある育て方に問題はなかったのだろうが
やはりミワも高校生から反抗期に似た時期がおとずれグレた。道をそれた。エリート進学校のお嬢様が突然“崩れた”ことは村田家を揺らした。東京山手銀行で厳しく50人の部下を牽引する村田も娘への対応は、赤子を包むように荒げさせないよう配慮してしまうのであった。
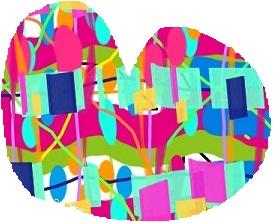
お腹がすくといつも荒れる口調のミワ。
「パパ、ミワと電話するときはいつもビデオ通話にしろ。いつもいってるだろが。あん?さびしいんだから。パパのベンツ待ってるですよ。9時に来いよ。」
時計をチラリと見ると夜の8時半。ここまるなが編集所の人形町からハナブサ商事まで車で30分圏内。特に大きな渋滞や夜間道路工事など出遭わなければ間に合う。村田がビデオ通話に切り替え、返事をする。
「ミワ、パパだよ。見えるかな。すぐ行くから待っててね。」
村田はまるなが編集所の福田への次回の会う予定を取り付け、いそいそと
自分のベンツへと乗り込んだ。大事な取引先の常務、重役をこの車に乗せることもあり、清潔で煙草の灰一つ落ちていないよう気づかっている。もちろん、毎日の
愛娘の”アシ”としても使う。
11月も半ば、東京の外の空気も肌寒さを与える頃。まるなが編集所は、午後3時の休憩どきが一日の中で唯一くつろげる時間である。秋の紅茶は一番おいしいとサエは思っている。
「月刊誌マチネタの記事、あなた、となり町の音舞町を取材してるんだったわね。まだ、発売まで時間あるし、原稿の赤入れは直せるから、再度取材いってきてちょうだい。原稿うまく書こうと考えすぎなくていいから。」
まだあたたかい紅茶を飲みながら福田編集長の右腕リリはそう伝えた。締め切りもいつも守れないスーパーマイペースの編集長。リリは舵を取るつもりではないのだがどうしても皆の進捗状況や各々の書いている記事を把握していないといられないのだ。入社10年目になり、次期編集長の声も得意様やまわりの社員からあがるが、福田の今思うところはリリではないみたいなのだ。
(原稿うまく書こうと思うのが普通だよなあ。発行まで3週間かあ。)
サエは、ぼんやりぼんやり都電東福線に乗り音舞駅に着いた。
ジュワージュワー。駅前のロックンドーナツに入ると、おやつ時なのか学校帰りの生徒たちが多いせいなのか、フライヤーがフル回転しており揚げる音、ふんわりしたあの甘い香りが充満する。ウェーブのかかったロングへアーと首元に長くだらんとした赤と緑のアクセサリーを着けた店員が揚げては並べ揚げては並べを繰り返している。サエは、とりあえずその様子を頭の中で描写することしかできなかった。
(先月のはじめ取材の前に寄ったけど覚えているのかな?私のこと。)
サエは、ふと周りを見渡した。みな、備え付けのアメリカナイズな感じのするベンチに腰をかけ本を読みながら食べる者、バンドの打ち合わせをしながら食べる者、お気に入りの写真を見せ合いながら愉しむ女の子たち...古めかしい内装にロカビリーが大きめの音量で店を流れる。
ドーナツを並び終えた店長の鳥本がこっちを見た。
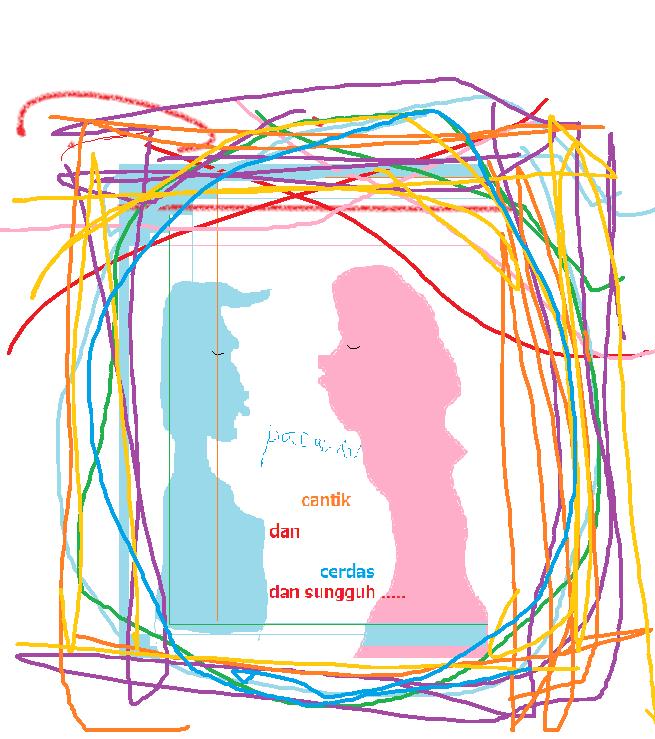
「ドーナツ、こちらでお召し上がりですか?揚げたてですよ。」
サエは、鳥本のひとりでテキパキ俊敏に働いている様子を店に来るといつも目にする。鳥本は長年大手スーパーマーケットやコンビニで主に発注・商品管理を任されてきた。昇進の話もあり、薦められたがずっと続けてきたロカビリーへのこだわりが捨てきれず20代の時一年ほどアメリカに渡った。演奏の練習の合間に食べた”お菓子”は、場を和ませてくれ少しではあるが根をつめた時などはリフレッシュ剤になった。毎日のように食べには来るもののとりたてて美味しいと思ってはいなかったが、いつもの自分の場所、いつものフラワードーナツが気持ちを落ち着かせた。堅苦しくなくていい気楽に入ってきてもらえる場所を自分も提供できたら.....と思いオープンしたのだった。
サエは、ここに来ると決まって買うのは、定番のロックンドーナツ1個とあたたかいブルーマウンテンを一杯。羽織っている黒のカーディガンの右ポケットから愛用のウサギマークの入った長財布を取り出した。500円がくれる秋の憩い。
精算も済み、店をあとにしようとしたその時会社から支給されている掌より少し小さいポケベルがサエを呼んでいる。まるなが編集所で唯一ポケベルを昔から使いこなしている福田編集長の提案で社員一同、出張または外出時はポケベルを持たせ連絡ツールとして使っている。
ピピーピピーピピー...
サエは、会社からの着信がなると急に落ち着かなくなる。
(ドーナツ屋さんの店長みたいにたとえ忙しい状況になっても落ち着こう。見習わなきゃ。でもだれからなんだろ。祐子先輩かな?)
ふとポケベルの伝言に目をやると21と入力されている。21は、ポケットベル定型伝言一覧表に当てはめて解読すれば「カイシャニTELシテクダサイ」と分かる。サエは、いま立っているところから右手に見える花屋の前の公衆電話に向かった。取材があれば、取材先とそこから最寄りの公衆電話を見つけておくことは、まるなが編集所では1年目の社員には徹底される。スマホが携帯が当たり前のようにある時代、公衆電話台数の激減によりテレホンカードがあまり市場に出回らない世情から考えるに、特に不便を感じるまるながの社員。

サエは、いつもの慣れた仕草で10円玉を入れ発信者の福田へ電話をかけた。
プルルルプルル... ガチャッ
「おつかれさま。ごめんねえ、サエちゃん。実はねえ、音舞駅付近も大事だったんだけどさあ、ビジネス経済の枠がまだだったのよお。とりいそぎハナブサ商事ってとこ行って来てくれるかしら。今日はご挨拶だけでいいわ。」
時刻はもうすぐ夜7時。ここまるなが編集所には、退勤時刻はない。
編集作業・取材記事の段取りなど各々が納得するまで夜遅くまで仕事を
進めていく。
「東京山手銀行の村田ですが。」
村田は東京山手銀行の頭取を務める。そしてここの出版する月刊誌ならびに
刊行物のファンであり時々こうやって編集長を訪ねる。
「あら、いつも足を運んでくださり申し訳ないです。あ、れいの用件で
お見えになられたのですね。どうぞお入りください。」
まるなが編集所の編集長、名前は福田紀子という。「きこさん」の愛称で
古くからの取引先からはそう呼び、親しみをもたれている。おっとり、ゆったり
落ち着きある性格のアラフィフの女性だ。
「こないだは村田家所有の島に行ってきなさいだなんて 唐突なこといって
すまんかった。ハハ。」
村田は、豪農の一家の長男として生まれた。幼いころから英数塾に通わせて
もらったり、ピアノを買ってもらったりした。お金で苦労はあまりなかった。
地元のエリート進学校を出て、東京大学に一発合格。進級するにつれ頼りになる
後輩が増え、その人脈が今でも生き現在も大手金融機関で支えている者が多くい
る。
ピリリリイ...村田の携帯電話が鳴る。ほぼ毎日ではないが夜に7時8時
ごろになると愛娘ミワから電話がかかってくる。着信通知を見ずにミワと分かる。
親の勘で。
「パパ、パパ、今どこにいるですか?パパ」
娘ミワは、関西の一流大学を卒業後、東京山手銀行の主要取引先の商社に勤めている。入社2年目ではあるが、現在はハナブサ商事の副社長のとなりで渉外の補佐役を務めたり新入社員のサワコの指導に当たったりと日々忙しくもある。
「おう ミワか。今日もごくろうさん。うむ、ミワ、ごめんね、取引先の
方と一緒でさ、今日は。ごめんね。ごめん。」
ミワは、一人っ子で愛情を十分にかけられ育ち、数え切れないほどのわがままを
村田に言ってそして甘えてきた。村田の愛ある育て方に問題はなかったのだろうが
やはりミワも高校生から反抗期に似た時期がおとずれグレた。道をそれた。エリート進学校のお嬢様が突然“崩れた”ことは村田家を揺らした。東京山手銀行で厳しく50人の部下を牽引する村田も娘への対応は、赤子を包むように荒げさせないよう配慮してしまうのであった。
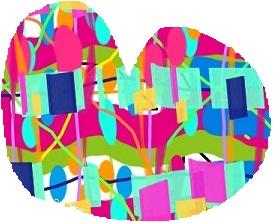
お腹がすくといつも荒れる口調のミワ。
「パパ、ミワと電話するときはいつもビデオ通話にしろ。いつもいってるだろが。あん?さびしいんだから。パパのベンツ待ってるですよ。9時に来いよ。」
時計をチラリと見ると夜の8時半。ここまるなが編集所の人形町からハナブサ商事まで車で30分圏内。特に大きな渋滞や夜間道路工事など出遭わなければ間に合う。村田がビデオ通話に切り替え、返事をする。
「ミワ、パパだよ。見えるかな。すぐ行くから待っててね。」
村田はまるなが編集所の福田への次回の会う予定を取り付け、いそいそと
自分のベンツへと乗り込んだ。大事な取引先の常務、重役をこの車に乗せることもあり、清潔で煙草の灰一つ落ちていないよう気づかっている。もちろん、毎日の
愛娘の”アシ”としても使う。
11月も半ば、東京の外の空気も肌寒さを与える頃。まるなが編集所は、午後3時の休憩どきが一日の中で唯一くつろげる時間である。秋の紅茶は一番おいしいとサエは思っている。
「月刊誌マチネタの記事、あなた、となり町の音舞町を取材してるんだったわね。まだ、発売まで時間あるし、原稿の赤入れは直せるから、再度取材いってきてちょうだい。原稿うまく書こうと考えすぎなくていいから。」
まだあたたかい紅茶を飲みながら福田編集長の右腕リリはそう伝えた。締め切りもいつも守れないスーパーマイペースの編集長。リリは舵を取るつもりではないのだがどうしても皆の進捗状況や各々の書いている記事を把握していないといられないのだ。入社10年目になり、次期編集長の声も得意様やまわりの社員からあがるが、福田の今思うところはリリではないみたいなのだ。
(原稿うまく書こうと思うのが普通だよなあ。発行まで3週間かあ。)
サエは、ぼんやりぼんやり都電東福線に乗り音舞駅に着いた。
ジュワージュワー。駅前のロックンドーナツに入ると、おやつ時なのか学校帰りの生徒たちが多いせいなのか、フライヤーがフル回転しており揚げる音、ふんわりしたあの甘い香りが充満する。ウェーブのかかったロングへアーと首元に長くだらんとした赤と緑のアクセサリーを着けた店員が揚げては並べ揚げては並べを繰り返している。サエは、とりあえずその様子を頭の中で描写することしかできなかった。
(先月のはじめ取材の前に寄ったけど覚えているのかな?私のこと。)
サエは、ふと周りを見渡した。みな、備え付けのアメリカナイズな感じのするベンチに腰をかけ本を読みながら食べる者、バンドの打ち合わせをしながら食べる者、お気に入りの写真を見せ合いながら愉しむ女の子たち...古めかしい内装にロカビリーが大きめの音量で店を流れる。
ドーナツを並び終えた店長の鳥本がこっちを見た。
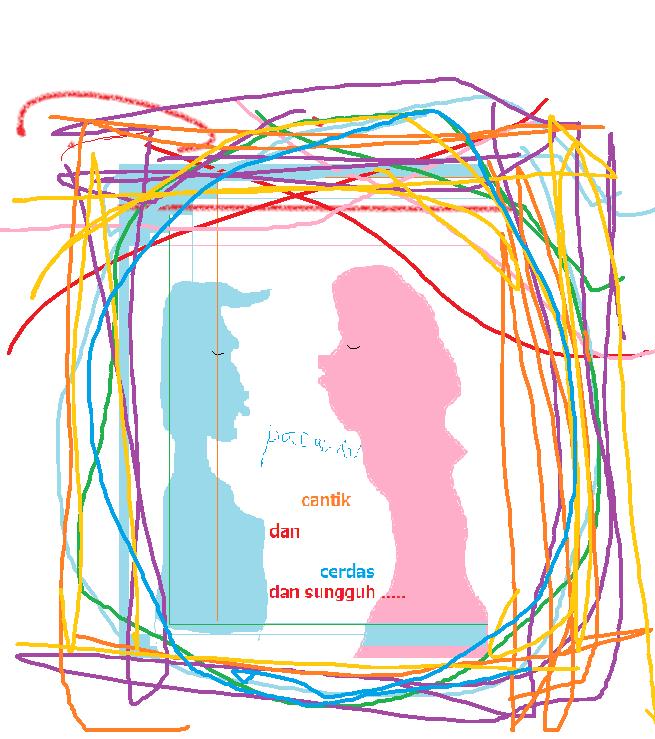
「ドーナツ、こちらでお召し上がりですか?揚げたてですよ。」
サエは、鳥本のひとりでテキパキ俊敏に働いている様子を店に来るといつも目にする。鳥本は長年大手スーパーマーケットやコンビニで主に発注・商品管理を任されてきた。昇進の話もあり、薦められたがずっと続けてきたロカビリーへのこだわりが捨てきれず20代の時一年ほどアメリカに渡った。演奏の練習の合間に食べた”お菓子”は、場を和ませてくれ少しではあるが根をつめた時などはリフレッシュ剤になった。毎日のように食べには来るもののとりたてて美味しいと思ってはいなかったが、いつもの自分の場所、いつものフラワードーナツが気持ちを落ち着かせた。堅苦しくなくていい気楽に入ってきてもらえる場所を自分も提供できたら.....と思いオープンしたのだった。
サエは、ここに来ると決まって買うのは、定番のロックンドーナツ1個とあたたかいブルーマウンテンを一杯。羽織っている黒のカーディガンの右ポケットから愛用のウサギマークの入った長財布を取り出した。500円がくれる秋の憩い。
精算も済み、店をあとにしようとしたその時会社から支給されている掌より少し小さいポケベルがサエを呼んでいる。まるなが編集所で唯一ポケベルを昔から使いこなしている福田編集長の提案で社員一同、出張または外出時はポケベルを持たせ連絡ツールとして使っている。
ピピーピピーピピー...
サエは、会社からの着信がなると急に落ち着かなくなる。
(ドーナツ屋さんの店長みたいにたとえ忙しい状況になっても落ち着こう。見習わなきゃ。でもだれからなんだろ。祐子先輩かな?)
ふとポケベルの伝言に目をやると21と入力されている。21は、ポケットベル定型伝言一覧表に当てはめて解読すれば「カイシャニTELシテクダサイ」と分かる。サエは、いま立っているところから右手に見える花屋の前の公衆電話に向かった。取材があれば、取材先とそこから最寄りの公衆電話を見つけておくことは、まるなが編集所では1年目の社員には徹底される。スマホが携帯が当たり前のようにある時代、公衆電話台数の激減によりテレホンカードがあまり市場に出回らない世情から考えるに、特に不便を感じるまるながの社員。

サエは、いつもの慣れた仕草で10円玉を入れ発信者の福田へ電話をかけた。
プルルルプルル... ガチャッ
「おつかれさま。ごめんねえ、サエちゃん。実はねえ、音舞駅付近も大事だったんだけどさあ、ビジネス経済の枠がまだだったのよお。とりいそぎハナブサ商事ってとこ行って来てくれるかしら。今日はご挨拶だけでいいわ。」


