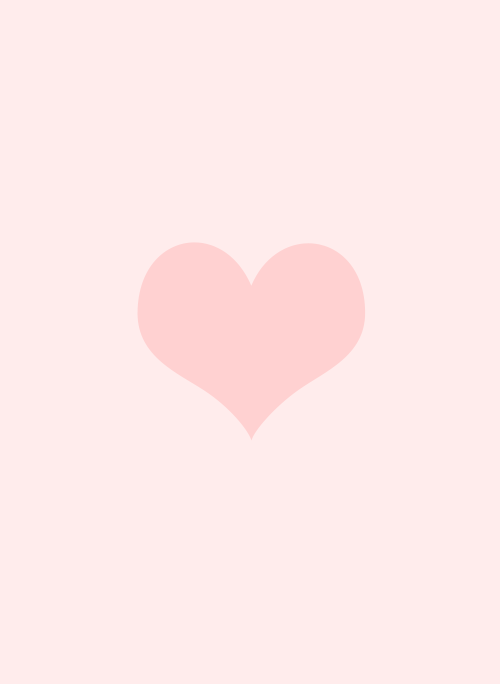木になった赤い実が揺れた。
手を伸ばし、私は。
出会いは最悪だった。その後の出来事を加算しても最悪な奴と言う印象は覆らなかった。
ショップバックに忍ばせたジャージを横目で睨み小さく息を吐いた。
「あんた、それ何?ジャージ?」
携帯電話のボタンを押しながらそう問うたのは、友人の一人。高校生になり一番仲良くなった友人。
「この間の朝絡まれたヤカラのジャージ」
言葉が足りない気もしたが、自分の中ではこれで十分な説明だった。
「ありゃ災難の一言じゃわ。で、なんでそんなヤカラのジャージをあんたが持っとるん」
友人には、何も教えていない。知っているのは、朝の出来事だけ。
「なんでじゃろう、私もよう分からん」
知らなくていい。陸と私のその後なんて。知ったところでそれはクラスの隅っこで燃える程のゴシップではないのだから。
「え……椿西高校……あんた!なんね!厄介なんに引っ掛かっとるでねぇの!」
するりとショップバックから抜き取ったジャージを広げ、友人が血の気の引いた顔で小さく悲鳴をあげた。まるで汚物を触るかのように親指と人差し指でつまむ姿に少しイラッとする。
「勝手に触らんとって」
「借りたん?もぅ!!早いとこ返し。椿西なんて柄悪いんじゃけ、関わっちゃいけん!!」
机を強く叩く友人を見ながら、私は今日、また会えるのだろうかと空を見た。上の空の私をよそに友人は何かを吠えているが聞こえない。
七月の手前。空は快晴。今年の梅雨は例年よりも早足だった。
あの夜、引き寄せられ胸に顔を埋めた。汗と制汗剤が混じる若い男子の香りと言えばいいだろうか。頭がクラクラと揺れる香り。
「なんで嫌がらんのじゃ」
一番最初に旋毛に降ってきた一言はこれだった。旋毛を跳ねた言葉に静かに言う。
「嫌じゃないからと違う?」
陸の香りと雨が乾くのを嫌がる香りを胸いっぱいに吸い込みながらそう答えると次に降ってきたのは笑い声。
「最低がお似合いの男なんじゃろう……そんな男に抱き締められても嫌じゃないならお前も同類じゃ」
そうかもしれない。
私の頬を押したり引いたりする胸目がけて言葉にならない大きさで呟いた。
「意味わからん」
腕を回される訳でも無く、ただあいつの心臓の音がダイレクトに鼓膜を揺らす。誰も見ていないこの狭い密室。
何も生まれない、何も芽生えない。
それでも何かに沈む感覚に飲み込まれる。鳩尾からじわりじわりと喉に上がる、締め付けられる感覚に頭が麻痺してしまいそうだった。
足りないと思っていた何かを、見つけた気がした。
手を伸ばし、私は。
出会いは最悪だった。その後の出来事を加算しても最悪な奴と言う印象は覆らなかった。
ショップバックに忍ばせたジャージを横目で睨み小さく息を吐いた。
「あんた、それ何?ジャージ?」
携帯電話のボタンを押しながらそう問うたのは、友人の一人。高校生になり一番仲良くなった友人。
「この間の朝絡まれたヤカラのジャージ」
言葉が足りない気もしたが、自分の中ではこれで十分な説明だった。
「ありゃ災難の一言じゃわ。で、なんでそんなヤカラのジャージをあんたが持っとるん」
友人には、何も教えていない。知っているのは、朝の出来事だけ。
「なんでじゃろう、私もよう分からん」
知らなくていい。陸と私のその後なんて。知ったところでそれはクラスの隅っこで燃える程のゴシップではないのだから。
「え……椿西高校……あんた!なんね!厄介なんに引っ掛かっとるでねぇの!」
するりとショップバックから抜き取ったジャージを広げ、友人が血の気の引いた顔で小さく悲鳴をあげた。まるで汚物を触るかのように親指と人差し指でつまむ姿に少しイラッとする。
「勝手に触らんとって」
「借りたん?もぅ!!早いとこ返し。椿西なんて柄悪いんじゃけ、関わっちゃいけん!!」
机を強く叩く友人を見ながら、私は今日、また会えるのだろうかと空を見た。上の空の私をよそに友人は何かを吠えているが聞こえない。
七月の手前。空は快晴。今年の梅雨は例年よりも早足だった。
あの夜、引き寄せられ胸に顔を埋めた。汗と制汗剤が混じる若い男子の香りと言えばいいだろうか。頭がクラクラと揺れる香り。
「なんで嫌がらんのじゃ」
一番最初に旋毛に降ってきた一言はこれだった。旋毛を跳ねた言葉に静かに言う。
「嫌じゃないからと違う?」
陸の香りと雨が乾くのを嫌がる香りを胸いっぱいに吸い込みながらそう答えると次に降ってきたのは笑い声。
「最低がお似合いの男なんじゃろう……そんな男に抱き締められても嫌じゃないならお前も同類じゃ」
そうかもしれない。
私の頬を押したり引いたりする胸目がけて言葉にならない大きさで呟いた。
「意味わからん」
腕を回される訳でも無く、ただあいつの心臓の音がダイレクトに鼓膜を揺らす。誰も見ていないこの狭い密室。
何も生まれない、何も芽生えない。
それでも何かに沈む感覚に飲み込まれる。鳩尾からじわりじわりと喉に上がる、締め付けられる感覚に頭が麻痺してしまいそうだった。
足りないと思っていた何かを、見つけた気がした。