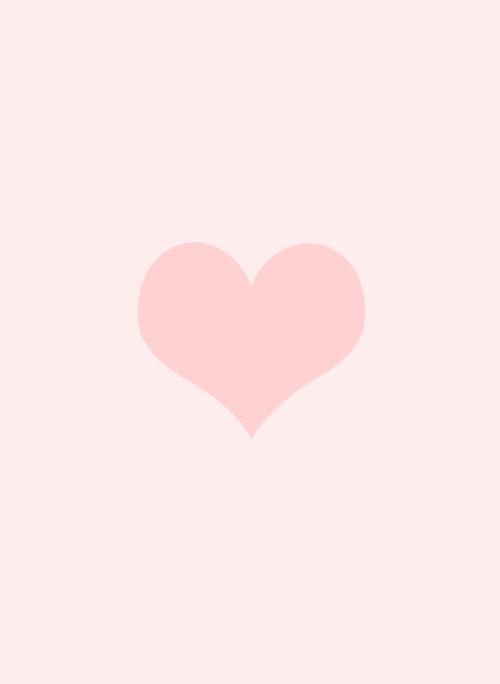リリーが手で顔を覆いながら、会場を出て行く。俺は女性に何も言わず、振り返りもせずにリリーの後を追った。
リリーは、パーティー会場から出てすぐの場所で、座って泣いていた。体を震わせ、嗚咽が漏れている。
俺はリリーに近づき、リリーの隣に腰掛ける。そして優しくリリーを抱きしめた。
「……一生懸命、あの人は働いてた……」
抱きしめられたことに驚きもせず、リリーは何があったのかを話し出した。俺は黙って耳を傾ける。
「……私たちだけが楽しむなんて、おかしいって思った……。一生懸命用意してくれた人にも、楽しんでもらいたいって……そう思ったから、ダンスに誘ったの……」
リリーが俺を見つめる。涙は止まることなく流れ続けている。
「貴族なんて、大っ嫌い!!王族はもっと嫌い!!……どうして、私はあんな家に生まれたんだろう」
「……お前は、世界平和対策本部の仲間だ。貴族じゃない」
俺は心に思っていることを、口にした。
「お前は優しく、まっすぐだ。そんな貴族を俺は知らない。お前のおかげで、俺や対策本部のメンバーは一つになれたんだ。……ありがとう」
リリーがパーティーを開催してくれたおかげで、俺たちの絆が深まり、互いを知ることができた。リリーがいつもきっかけを作ってくれているのだ。
「リーバス、帰ろう。……もう、ここにはいたくない」
リリーは、パーティー会場から出てすぐの場所で、座って泣いていた。体を震わせ、嗚咽が漏れている。
俺はリリーに近づき、リリーの隣に腰掛ける。そして優しくリリーを抱きしめた。
「……一生懸命、あの人は働いてた……」
抱きしめられたことに驚きもせず、リリーは何があったのかを話し出した。俺は黙って耳を傾ける。
「……私たちだけが楽しむなんて、おかしいって思った……。一生懸命用意してくれた人にも、楽しんでもらいたいって……そう思ったから、ダンスに誘ったの……」
リリーが俺を見つめる。涙は止まることなく流れ続けている。
「貴族なんて、大っ嫌い!!王族はもっと嫌い!!……どうして、私はあんな家に生まれたんだろう」
「……お前は、世界平和対策本部の仲間だ。貴族じゃない」
俺は心に思っていることを、口にした。
「お前は優しく、まっすぐだ。そんな貴族を俺は知らない。お前のおかげで、俺や対策本部のメンバーは一つになれたんだ。……ありがとう」
リリーがパーティーを開催してくれたおかげで、俺たちの絆が深まり、互いを知ることができた。リリーがいつもきっかけを作ってくれているのだ。
「リーバス、帰ろう。……もう、ここにはいたくない」