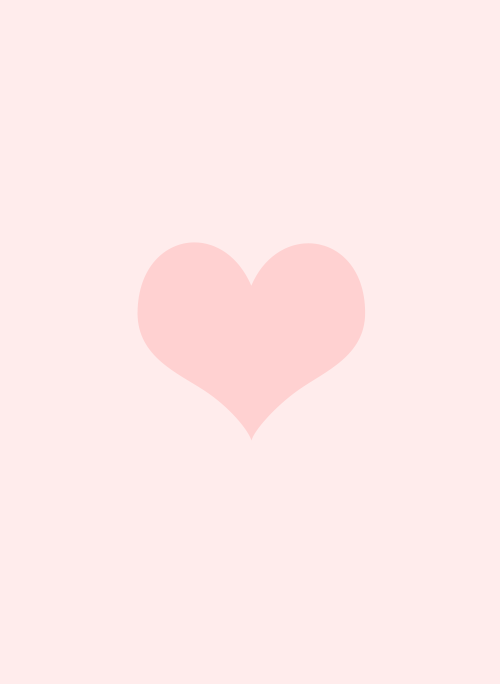傷つけるとでも思ってしまったのか。しかし、それは京ちゃんが感じた事実だったのだ。受け入れる他ない。
それとも、言い返してやれば良いのだろうか。
酷い。何でそんな事言うの。私だって。などと。
けれど、実際、私は言い返す言葉など持ち合わせていなかった。
「千花にとっては何でもない事でも、私は確かに千花に救われた。だから今こうして頑張ろうって思えた」
「……うん、ありがとう」
「それなのに、その千花が自分を蔑にしてるのが許せない。何で、何で……っ!……私の憧れたカッコいい千花でいてくれないの……っ?」
堪え切れなくなった涙が溢れて零れて、俯いていた昔の彼女が顔を出した瞬間、顔を背けて私の横をすり抜けて行った。
振り返る事も出来ず、声を掛ける事も出来ず、その場に立ち尽くすしか出来ない。
不意吹く温くて気持ち悪い風が体の中の倦怠感を煽り、私はゆっくりとその場にしゃがんだ。
「どうすればよかったのかなぁ……」
何回も何十回も思った事を口から滑り落としてしまえば、更に空しさが加速してどうしようもなくなる。
情けない事に、泣いてしまいたいとさえ思ってしまった。