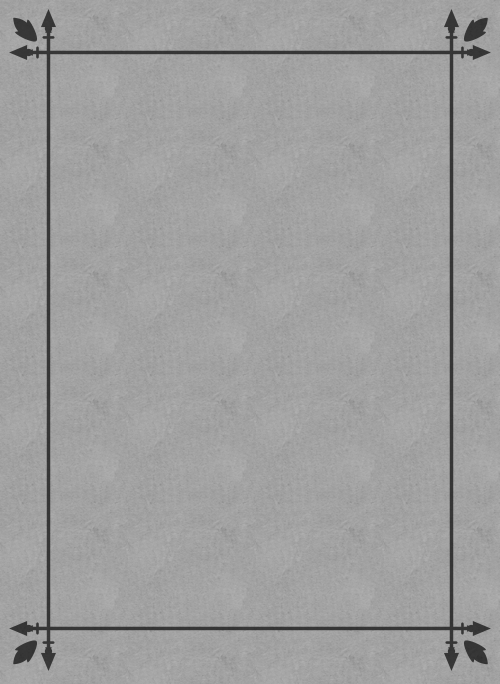誰が能力者なのかは、誰にも見た目で判断することはできない。姿形は一般人と全く変わりがないからだ。
物語のように、目が赤くなるだの、髪の色が変わるだの、そんなことは一切ない。
だからこそ、見分けることができず能力者の捕獲は難航する。
能力者自身が自分から能力を持っていると公言するか、能力を実際に目にして初めて能力者かどうかが分かる。
公言もしない、能力を使っている所さえ見られなければ一般人に紛れ込んでもバレることはない。
人々は命をいつ、誰に吸い取られるか分からない恐怖に駆られた。
隣で笑っている人が、次の瞬間には自分の命を狙うかもしれない。
誰を信じれば良いのか分からない。常にどこかで警戒をした状態で生活していかねばならない。
そんな中、能力者を見つけ出し命の期限を伸ばして欲しいと縋り付く人物達も現れた。
能力者側も同じ。自分の不死身の為に命を奪い、この世界を永遠に見守り続けて行こうと言う人間と…。
金儲けをし、良い生活を送りたいがために商売として力を使うものに分かれた。
そして、それは同じ思想の人間を吸収しながらどんどん大きな組織となっていく。
以前は国の機関の下、秩序を守るための掟の元でしか動くことのなかった道具であった能力者達は変わらず国の管理の下、これまで以上の優遇した生活を約束された代わりに能力を生かし、人々に分け与えようという派閥、白命(はくみょう)と。
人に命を与えたりはしない。命を奪うことを目的とする国の意向に背く派閥、黒命(こくみょう)に。
そして、もう1つ。
そんな能力を持った人間を排除しようとする機関ができた。
長年、能力者たちを管理していた国が作り出した”組織”。
能力者の排除を目的とした組織が作り出された。
能力者は命を奪えば延命できるが、それはあくまで何もなければ、の話。
稀に能力者の中には病気やケガを治す、治癒力に秀でた能力も持っている者がいるが。
体に外傷を受け、心臓が止まれば普通の人間と同じで、死ぬのだ。
排除。つまりこの世界から消す。捕えて、殺す。
それだけを目的とした機関。
今まで国に管理されていた外の世界を何も知らない能力者たちと、全てを知っている国では力の差は歴然であった。
結果的にその機関と、能力者を恐れるあまりその機関の配下についた凡人達の力で、粛清が行われ能力者の人口は激減。
最初は能力者の減少に渋っていた国の幹部も…
自分たちの元で管理できないのならば脅威にさらされることよりも絶滅を望んだ。
そして、力を入れられた国に住んでいる能力者は勝てるはずもなく、少しずつ、減っていた。
だが、まだ能力者はいて、力を使いながらこっそり生活をしている。
「……命の丘のある街には確実に能力者がいるという。
人の命を狩ったかと思えば、その命与える人間が。
いい方に使えば、命を与えられる。
悪く使えば命を奪える。
都市伝説と言われているが、ある時は寿命をのばす助けをし、ある時は狩るとも。
普段は一般人と同じなので、いつ、どこで襲われるかわからない。
100年前、処分された能力者たちが眠っている命の丘で、依頼はできるとされている。
本当かどうかは、知らないーーが、延命を望む人、奪ってほしい相手がいる人はぜひ訪れて依頼してみるといい―――」
男は、暗闇の中見つめていた文字の羅列からそこで視線を逸らした。
「本当かどうかは知らないーーね、」
最後に読んだ一言をもう一度復唱すれば、自然と出てくる笑み。
書いたのは誰かわからない。
同じ能力者なのか、それともただの一般人なのか。
ーー半分嘘で、半分本当だ。と思う。
こんなたった数枚にしかならない文章で、あの事件がまとめられているとは。
「……命の丘ねぇ」