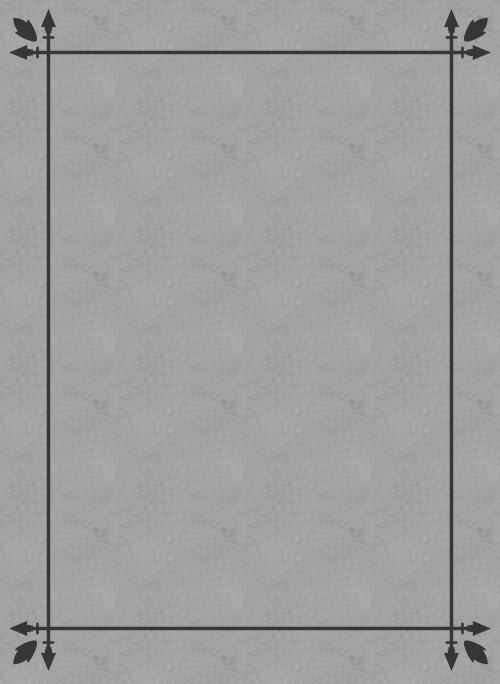この場に不適切だが笑みがこぼれる。
「車は」
「もう一件通夜が入ってるとのことでスタッフに言われ駐車場に待機してます」
「早く呼べ」
「ここでお待ちください」
入口には、重ならないようにと時間がずらされているのだろう。
おそらくもう一件の通夜の参列者だと思われる人々の車が次々と入ってくる。エンジン音がうるさく、専務を待たせ通話環境のいい場所を探すように離れる秘書。
「…すみません専務」
「…?」
振り返った男は、声をかけてきた男を見る。スーツに白い紙袋を持った男。
メガネ越しに見える相貌から足元まで眺めた後で声をかけた男が口を開く。
「本当にありがとうございました。叔父も喜んでいると思います。これ…さっき渡すのを忘れておりまして。よろしければ、」
そういい自分の顔の前に紙袋をかかげ、専務へと渡す。
そこまできて、専務はこの男が遺族だと認識する。
車が遅いことにイラついていた表情をまた、胡散臭い笑顔へと変えた。
「あぁ、いいのに。…わざわざすみません」
「いえ。…おっと専務」
一歩。踏み出した男に専務は紙袋を受け取ったまま、首を傾げる。
紙袋を渡したことで手ぶらになった手が、胸元へ。
「ーーー……」
「さすが専務。ネクタイも肌触りが違いますね」
にっこりと男が笑えば、専務も笑い返す。
きちんと正されたネクタイ。
「…本当にありがとうございました。…お気をつけて」
「あぁ、失礼します」
頭を下げて、自動ドアの中へと入って行った男。
…普通ならば。
最期まで見送るだろうことに違和感を感じなかったのは。
早く帰宅したかったからか、
褒められて気分が良くなっていたからか。
「お待たせしました。後ろにつけてます」
「あぁ」
ようやく家に帰れる。