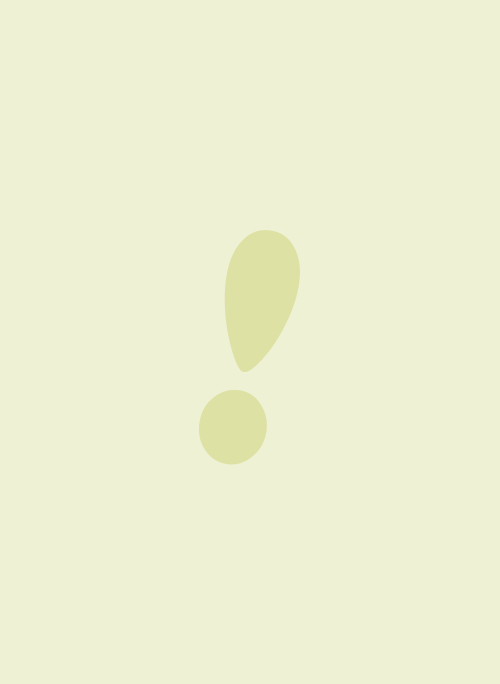いつもの暗い夜道を歩いてた。
いつもの帰り道。
歩道橋があって、
チェーンのファミレス通り、
カラオケ店にDVDのレンタルショップを通って
横断歩道を渡って駅前に着く。
私が路上ライブやってる駅だ。
そして、もうすぐ家に着く。
終電がとっくに終わってたからかものすごく静かだった。
いや、違う。人がいないから静かに感じるんじゃない。
はやとがいないからだ。
歩道橋ではいつもはやととふたりで叫びまくって楽しんだ。
ファミレスでははやととふたりでよくご飯を食べて時間がわからなくなるくらいしゃべりまくった事もあった。
カラオケ店ではストレスが貯まってた私にいち早くはやとは気づいてくれて、よくオールして一緒に歌いまくった。
レンタルショップでは私が苦手なのを分かってはやとはわざとホラーを借り、うちで一緒に見たが私のビビりようにいつもはやとは大笑いしていた。
駅では私の路上ライブをはやとはいつも見に来てくれた。
そんな事を駅前のベンチに座りながら考えていた。
ふたりでいることが普通過ぎて、ひとりでこうやって過ごす事がものすごくものすごく静かで寂しくてたまらない。
ヤバイ、涙が出てきた。
涙が止まらない。
寂しい。寂しいよ……はやとー!
はやと「なに泣いてんだよ‼だから、送るって言っただろ!」
私はびっくりした。
なんで、はやとがここにいるのか…
ゆうき「なんで?」
はやと「いや、追いかけてきた。」
ゆうき「ゆいかちゃんは?」
はやと「『今日ではやとさん好きなの最後にします。私はひとりで帰ります。』ってさ。」
ゆうき「なんで?あんなにガンガンに押しまくってたのに…」
はやと「さあな。でも、よかった。また、ゆうきが普通に話してくれてさ。」
ゆうき「…あ…いや…」
はやと「何だよ、まただんまりか?」
ゆうき「………」
はやと「でも、さっきはいつものゆうきだったから安心したよ。なんか悩んでるんだったら聞くから。誰かに話を聞いてほしい時はいつでも呼べよ!」
はやとはいつもの笑顔で言った。
私はその笑顔を見たら、自然に言葉が出た。
ゆうき「言えるわけないじゃん…はやとの事なんだからさ。」
はやと「え?」
ゆうき「この前の打ち上げの日から変なんだ。あの時の言葉を聞いたあの瞬間から何もかもが違うくなった。はやとの事ばっか考えて、でも、どう接していいかわかんなくなって…今回ばっかりは思ったよ、女子っぽかったらよかったのにって。この男っぽさがはじめて嫌になったよ。」
はやと「…男なんかじゃない。」
ゆうき「え?」
はやと「俺にとってはゆうきははじめから男なんかじゃない。最初っから、女だった。男だなんて思った事1度もねぇよ。俺はこれでもずっとゆうきが好きだったんだけど誰かさん、全く気がつかねぇんだもんな。」
ゆうき「ごめん。でも、彼女いた事あったじゃん。」
はやと「ああ…付き合ってくれた子達には本当に申し訳なく思ってる。俺が彼女作ったのゆうきへの気持ち消すためだったから。まあ、結局、ダメでたくさん傷つけたけど…」
ゆうき「…ごめん。」
はやと「お前のせいじゃねぇよ。俺が中途半端な事したからだ。でも、ゆうきが俺の事好きになるのはさすがに諦めてたから油断してたよ。気付けなかった。なあ、ちゃんと俺見て言ってくれないか。」
ゆうき「え!?恥ずかしいよ!」
はやと「わかってるよ。俺だって男のくせにこんな事言ってる自分にすんげぇ照れてんだからよぉ。でも、ちゃんと実感したいんだよ。」
ゆうき「………あ゛ー、もう!わかったよ!
………私ははやとの事が…好きです…あ゛ー、やっぱ、恥ずかしい。」
私は恥ずかしさのあまりベタに両手で顔を隠した。
はやとは私のその手をどけてキスをした。
そして、言った。
はやと「長い間、想ってたんだ。これから覚悟しとけよ!もう俺我慢するの無理だから。」
私達は笑い合い。
私達はまたキスをした。
はやとらしい力強くも優しいキスだった。