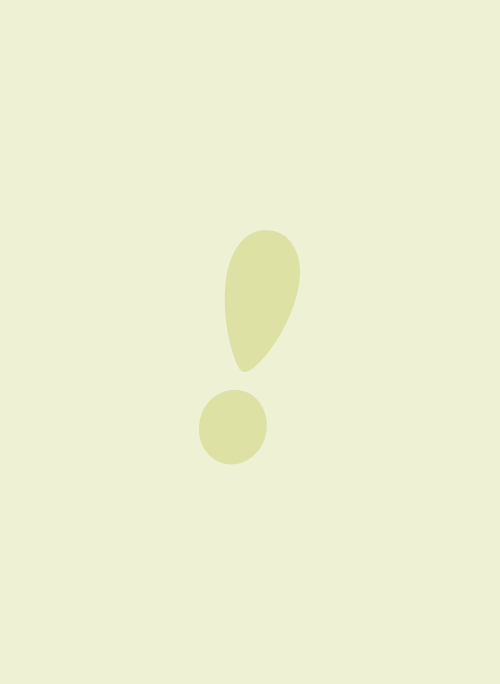握られた手を引き寄せられ陽亮の腕の中にいた。
「好きだから……嫌いにならないでくれ」
包みこむよう背中に置かれた陽亮の手と、今までで1番近くに感じる陽亮が現実だと認識しだす。
「ホントに?嘘じゃなくて?」
ドキドキとか恥ずかしいとかそんなもの通り越し、ただ触れられた箇所が熱い。
「本気の本気」
一度身体を離し、私の目を真剣に見つめる陽亮からは嘘じゃないって伝わってきた。
優しく微笑み、流れ出していた涙を同じくらい優しい手つきで拭いてくれる。
「俺と付き合って欲しい」
前みたいないい加減な言い方じゃなくて、向き合って言われるとやっと実感出来た。
出来たけど嬉しすぎて『はい』の一言が出てこない。
「……すぐじゃなくていいから考えてくれる?そうだな……クリスマスイヴ、デートしない?それまでに考えておいて」
言いそびれてしまったことで、陽亮は私が迷ってると勘違いしたみたいで困ったような顔をしている。
それが少し可愛らしくて、私も勘違いだったとはいえ先延ばしにしていじわるしたくなってしまった。
わかったとだけ言うと、また家まで送ってくれた。
その帰り道は行きと違って幸せで、お腹が空いていたのにこのままずっと帰りたくないと思えるほどだった。
「好きだから……嫌いにならないでくれ」
包みこむよう背中に置かれた陽亮の手と、今までで1番近くに感じる陽亮が現実だと認識しだす。
「ホントに?嘘じゃなくて?」
ドキドキとか恥ずかしいとかそんなもの通り越し、ただ触れられた箇所が熱い。
「本気の本気」
一度身体を離し、私の目を真剣に見つめる陽亮からは嘘じゃないって伝わってきた。
優しく微笑み、流れ出していた涙を同じくらい優しい手つきで拭いてくれる。
「俺と付き合って欲しい」
前みたいないい加減な言い方じゃなくて、向き合って言われるとやっと実感出来た。
出来たけど嬉しすぎて『はい』の一言が出てこない。
「……すぐじゃなくていいから考えてくれる?そうだな……クリスマスイヴ、デートしない?それまでに考えておいて」
言いそびれてしまったことで、陽亮は私が迷ってると勘違いしたみたいで困ったような顔をしている。
それが少し可愛らしくて、私も勘違いだったとはいえ先延ばしにしていじわるしたくなってしまった。
わかったとだけ言うと、また家まで送ってくれた。
その帰り道は行きと違って幸せで、お腹が空いていたのにこのままずっと帰りたくないと思えるほどだった。