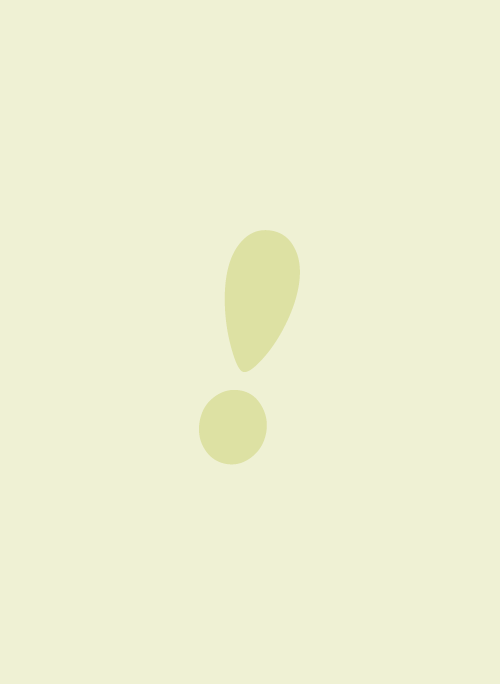陽亮と目が合うと、時間が止まったかの様にただ波の音だけが私たちを包んでいる。
陽亮の手がゆっくりと私の顔に近付いてくるのを止める事も出来ず、一瞬私だけの時が止まってしまったかのような錯覚にも陥る。
不意に、どこからか転がってきたビーチボールが時を動かした。
小さな子供がそれを取りに来た時に急に恥ずかしさと、自分がたった今何をしようとしていたか訳のわからない感情に押し寄せられた。
陽亮の手は私の顔に触れる前に止められ、子供が来た事で空を掴む形で引っ込められた。
「あのさ……」
「じゃ、じゃあ私行くね‼これあとは自分でやって」
陽亮が何を言いかけたのか聞きたいけれど聞きたくない気がして、スプレーの缶を陽亮の手の中に残してサクラたちの元へ走り出す。
あ……危なかった~
走りながらも今自分が陽亮の持つ空気に流されそうで、危うく『一夏の経験』をしてしまいそうだった事に胸がドキドキと高鳴る。
戻ったら、みんなに『顔が赤いよ?』なんて茶化されたけれど、まだ高鳴る鼓動がうるさくて耳に入らなかった。
帰りの電車の中もサクラたちは疲れて眠ってしまっていたけれど、私はビーチで眠ってしまった事もあり眠れなかった。
電車の窓から移りゆく景色がとてもゆっくり感じられ、行きよりも長く感じられた。
でも、陽亮の傍で感じた時間より長いものは今まで無かった気がして、少しだけ鼓動がおさまってきたように思えた。
陽亮の手がゆっくりと私の顔に近付いてくるのを止める事も出来ず、一瞬私だけの時が止まってしまったかのような錯覚にも陥る。
不意に、どこからか転がってきたビーチボールが時を動かした。
小さな子供がそれを取りに来た時に急に恥ずかしさと、自分がたった今何をしようとしていたか訳のわからない感情に押し寄せられた。
陽亮の手は私の顔に触れる前に止められ、子供が来た事で空を掴む形で引っ込められた。
「あのさ……」
「じゃ、じゃあ私行くね‼これあとは自分でやって」
陽亮が何を言いかけたのか聞きたいけれど聞きたくない気がして、スプレーの缶を陽亮の手の中に残してサクラたちの元へ走り出す。
あ……危なかった~
走りながらも今自分が陽亮の持つ空気に流されそうで、危うく『一夏の経験』をしてしまいそうだった事に胸がドキドキと高鳴る。
戻ったら、みんなに『顔が赤いよ?』なんて茶化されたけれど、まだ高鳴る鼓動がうるさくて耳に入らなかった。
帰りの電車の中もサクラたちは疲れて眠ってしまっていたけれど、私はビーチで眠ってしまった事もあり眠れなかった。
電車の窓から移りゆく景色がとてもゆっくり感じられ、行きよりも長く感じられた。
でも、陽亮の傍で感じた時間より長いものは今まで無かった気がして、少しだけ鼓動がおさまってきたように思えた。