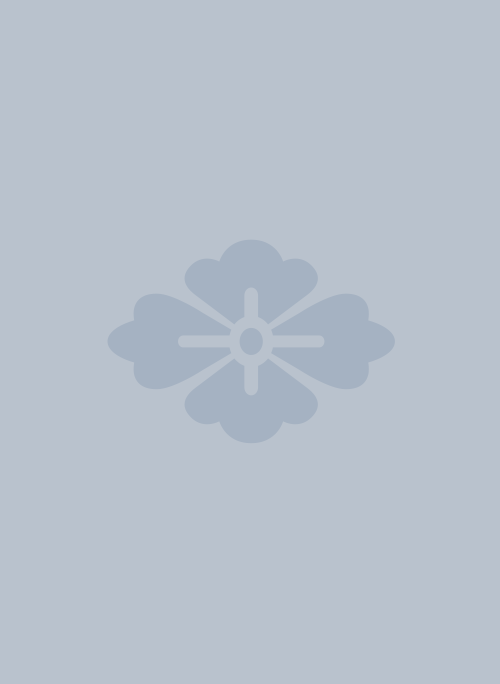自分の腕に小刀を当てて、そして、やめた。
自分の手を汚したくなかったのか、いや、違う。
怪我をするのが嫌だったのだ。
既に紅い衣裳が、黒さを増すのが、嫌だったのだ。
当時、霛塋は数えの五つだった。
榮氏は霛塋の小さな手を取って、それに冷たい、硬いものを当てていた。
目隠しをされていた。
何も、見えなかった。
避けられなかった。
鋭い刃は、肉を抉った。鮮血が、流れに流れ、死ぬかもしれない事態にまでなった。
自分の手を汚したくなかったのか、いや、違う。
怪我をするのが嫌だったのだ。
既に紅い衣裳が、黒さを増すのが、嫌だったのだ。
当時、霛塋は数えの五つだった。
榮氏は霛塋の小さな手を取って、それに冷たい、硬いものを当てていた。
目隠しをされていた。
何も、見えなかった。
避けられなかった。
鋭い刃は、肉を抉った。鮮血が、流れに流れ、死ぬかもしれない事態にまでなった。