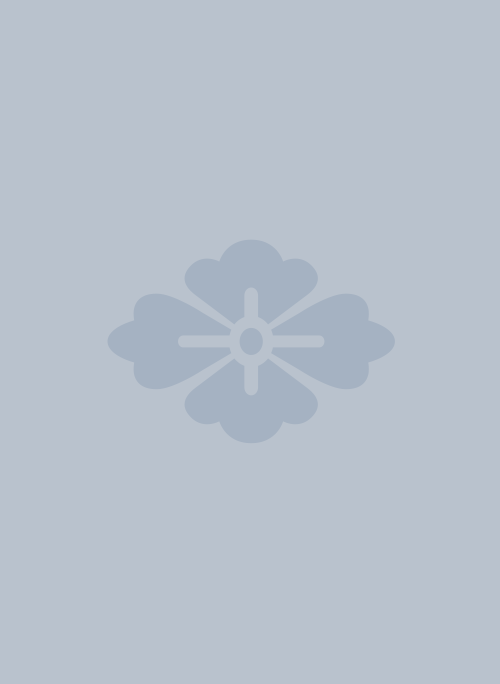「あ、良かった。いないのかと思ったよ」
玄関の戸を開けると、一気に西日が差し込んだ。眩しくて目を凝らす。
西日を背に立つのは、家庭教師の神崎 紬(かんざき つむぎ)。私がいると知って安堵したのか、メガネの柄を触る。
一切手を入れてない黒髮に色素の薄い茶色の大きな瞳が、成人した大学生とは思えない幼さを感じさせる。
「ごめんなさい」
言葉ばかりの謝罪なのに、彼は大丈夫だよと愛想よく微笑んでくれる。
挨拶もそこそこに部屋に通す。
ベッドと勉強机、それから本棚。
殺風景と思われるかもしれないが、身辺はすっきりさせた方が落ち着くし頭が冴える。
「誰かいるの?」
今日の分のプリントをカバンから出しながら、彼が聞いた。
「玄関に靴、あったけど。友達?」
私は答えなかった。
友達が私にいるかどうかなんて、彼は分かっているはずなのに。
「ほっといて大丈夫?」
顔を覗き込まれる。彼の手が私の手に微かに触れていた。
目を合わすのが嫌で、故意に逸らす。
「実花…」
「Please leave me alone」
「え?」
「私……そう言ったの」
私はあえて誰にとは、言わなかった。
彼もまた私に聞いてくることはなかった。
「他にも、…I didn't want to come such place……ってIt didn't want to be awayって…」