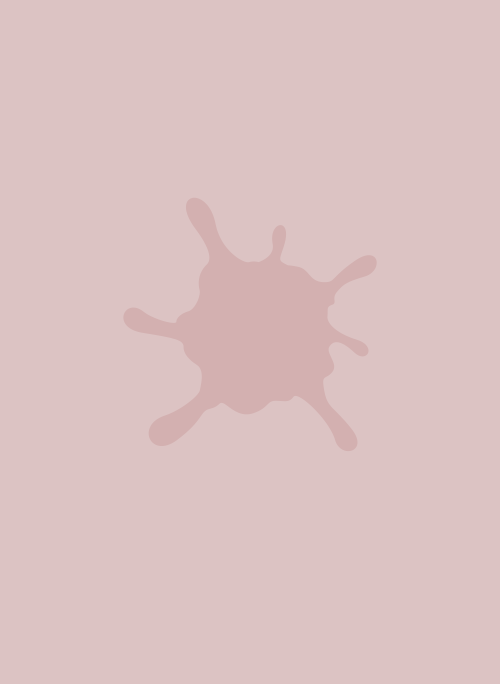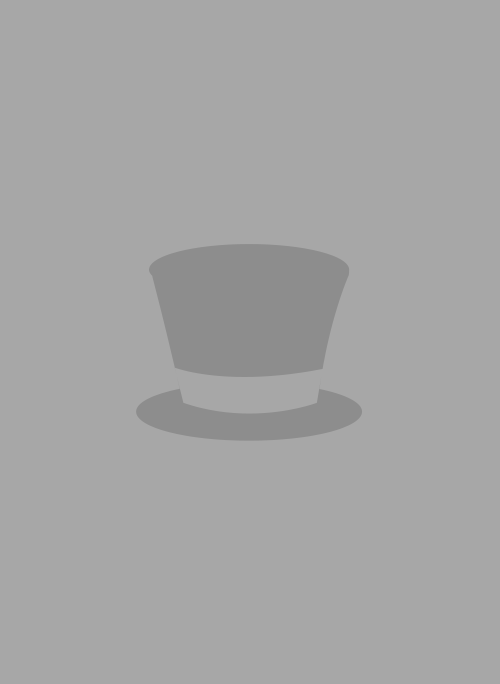私は気まずさをごまかそうと次の話題を探し、ふと思い出して尋ねました。
「そういえば容子、校長先生も知りたがってたよ。
容子が『夜の庭園』の話を誰から聞いたのか。ずいぶん昔の話なのにってーーー」
言い終わらないうちに、容子は足を止めました。
私を見る容子の顔は、夕闇の中でもはっきりと血の気が失せて見えました。
「......教えない」
薄く開かれたくちびるから、絞り出すように声が漏れました。
以前と変わらない答えに、私はまたムッとしながらも、ただならないものを孕んだ彼女の様子にそれ以上追求することができませんでした。
容子は再び俯いて歩きだし、私はそのあとを黙って追いかけました。
目の前に揺れるピンクのランドセルは迫る夜の中ですでに色をくすませ、その輪郭を翳る景色の中に溶かし始めていました。
「そういえば容子、校長先生も知りたがってたよ。
容子が『夜の庭園』の話を誰から聞いたのか。ずいぶん昔の話なのにってーーー」
言い終わらないうちに、容子は足を止めました。
私を見る容子の顔は、夕闇の中でもはっきりと血の気が失せて見えました。
「......教えない」
薄く開かれたくちびるから、絞り出すように声が漏れました。
以前と変わらない答えに、私はまたムッとしながらも、ただならないものを孕んだ彼女の様子にそれ以上追求することができませんでした。
容子は再び俯いて歩きだし、私はそのあとを黙って追いかけました。
目の前に揺れるピンクのランドセルは迫る夜の中ですでに色をくすませ、その輪郭を翳る景色の中に溶かし始めていました。