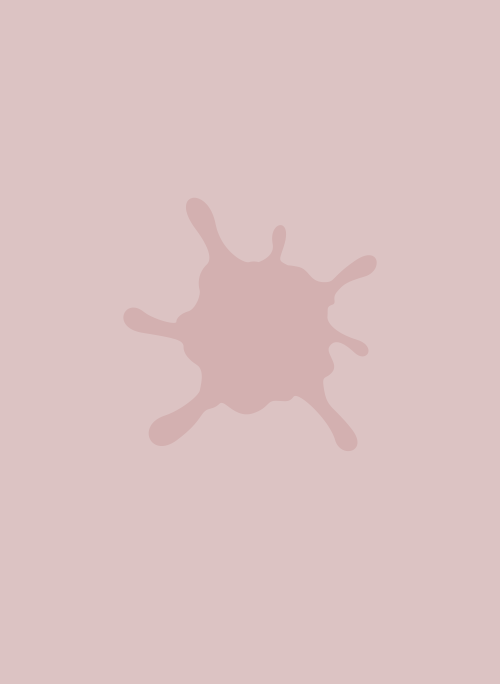そして予想通り、コロッケ、サラダ、フライドポテト、ご飯が並べられた。
数回しか使っていないドレッシングをこれでもかというくらい振る。そして、プチトマトが添えられたサラダに、玉ねぎのドレッシングをかける。
嵩張っているキャベツを箸で掴み、口に運んだ。
ソースをかけたコロッケのそばに箸を突き立て、距離を狭めていく。箸同士がぶつかったとき、サクサクのコロッケは千切れた。
昼ごはんを終えた私は、一人になりたくて自分の部屋に行った。
ストーブのつまみを回して、つまみの黒い点を強に合わせる。
ジジジと音を立ててストーブが熱を出す。じきに中の棒がオレンジ色に染まる。
私はスマホのマップを広げ、マラソン大会のスタート地点である公園を見つける。そこから走ってきた道を辿っていき、倒れたところで指を止めた。
葉科町か。
バスで一時間とちょっとかかる場所の聞いたこともないような町に、あの人はいる。
私の頭の中で、目を伏せたあの人が動かずに聞いていた。そして、長いまつ毛で隠れがちな黒い目を開け、立ち上がった。
家を出る前のその一瞬も綺麗だった。
突き当たりにある電話の音が遠く聞こえる。お母さんが声のトーンを上げている。筒抜けの声も今日は頭に留まらない。
こんなに人のことを綺麗だと思ったのは初めてだ。
あの人の姿をもっと見たい、あの日のことをもっと知りたい。今日のことだけでこんなに強い思いが生まれた。
あの人が何かの花や絵だったら、今手に持っているスマホで調べるのに。名前がわからなくても、思いつくワードを打ち込んで見つけ出す。それでもだめなら質問サイトを使う。
安芸津と打ち込んでもどうにもならないのがもどかしい。
私のこの感情はどこにやればいいの?
「しいちゃん、入っていい?」
お母さんは私が安芸津さんに助けられたことも、安芸津さんのことで頭が一杯になっていることも知らない。
それがなんだかおかしくて笑みが浮かんだ。
「うん」
白い扉が開き、お母さんの腕が現れた。
あ。
そういえば、学校で何かあれば電話をかけてくる。
私はやっと厄介なことに気付き、硬直した。
「電話がかかってきたんだけど、マラソン大会で倒れたんだって?もう、なんで言わないの……今はなんともないの?」
大丈夫、としか言えなかった。
そうだ、マラソン大会で倒れるって大変なことなんだ。助けられた後体が軽くなったから、そのことも抜け落ちてたけど……。
数回しか使っていないドレッシングをこれでもかというくらい振る。そして、プチトマトが添えられたサラダに、玉ねぎのドレッシングをかける。
嵩張っているキャベツを箸で掴み、口に運んだ。
ソースをかけたコロッケのそばに箸を突き立て、距離を狭めていく。箸同士がぶつかったとき、サクサクのコロッケは千切れた。
昼ごはんを終えた私は、一人になりたくて自分の部屋に行った。
ストーブのつまみを回して、つまみの黒い点を強に合わせる。
ジジジと音を立ててストーブが熱を出す。じきに中の棒がオレンジ色に染まる。
私はスマホのマップを広げ、マラソン大会のスタート地点である公園を見つける。そこから走ってきた道を辿っていき、倒れたところで指を止めた。
葉科町か。
バスで一時間とちょっとかかる場所の聞いたこともないような町に、あの人はいる。
私の頭の中で、目を伏せたあの人が動かずに聞いていた。そして、長いまつ毛で隠れがちな黒い目を開け、立ち上がった。
家を出る前のその一瞬も綺麗だった。
突き当たりにある電話の音が遠く聞こえる。お母さんが声のトーンを上げている。筒抜けの声も今日は頭に留まらない。
こんなに人のことを綺麗だと思ったのは初めてだ。
あの人の姿をもっと見たい、あの日のことをもっと知りたい。今日のことだけでこんなに強い思いが生まれた。
あの人が何かの花や絵だったら、今手に持っているスマホで調べるのに。名前がわからなくても、思いつくワードを打ち込んで見つけ出す。それでもだめなら質問サイトを使う。
安芸津と打ち込んでもどうにもならないのがもどかしい。
私のこの感情はどこにやればいいの?
「しいちゃん、入っていい?」
お母さんは私が安芸津さんに助けられたことも、安芸津さんのことで頭が一杯になっていることも知らない。
それがなんだかおかしくて笑みが浮かんだ。
「うん」
白い扉が開き、お母さんの腕が現れた。
あ。
そういえば、学校で何かあれば電話をかけてくる。
私はやっと厄介なことに気付き、硬直した。
「電話がかかってきたんだけど、マラソン大会で倒れたんだって?もう、なんで言わないの……今はなんともないの?」
大丈夫、としか言えなかった。
そうだ、マラソン大会で倒れるって大変なことなんだ。助けられた後体が軽くなったから、そのことも抜け落ちてたけど……。