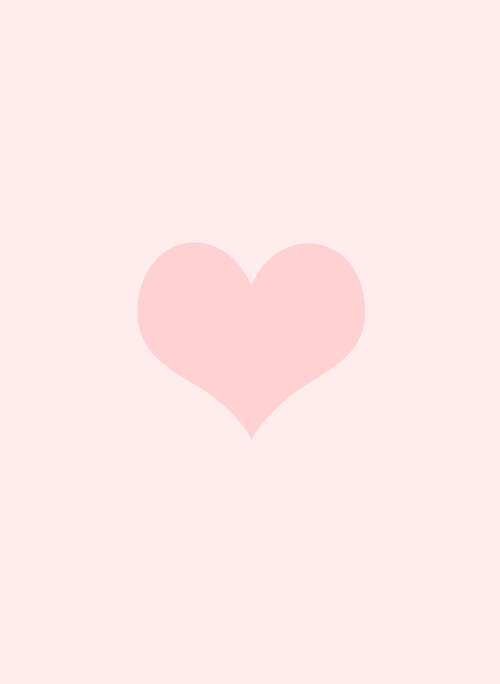モクモクと湯気を漂わせながら、彼が脱衣所の扉を開けて出てきた。
「いいお湯だったよ。千歳も入ったら?」
「ちょっと、自分の家みたいに言わないでよ。ていうか、わたしは入らないから」
「入らないって、…不潔だな」
「女の子にそんなこと言わないの。嫌われるよ」
「いやいや、ごめん。お願いだから嫌わないで」
彼の必死さに、わたしは思わず吹き出しそうになる。
「あんたのこと、嫌いはしないけど、相当怪しんでるよ」
「まぁ、そうだろうね」
彼は勝手にわたしのベッドに身を投げて、ボフンと音を立てて沈めた。
「もー、わたしの寝るとこ無くなるじゃん」
「え?本当は一緒に寝れるって喜んでるくせに」
「喜んで無いし」
そもそも、よく知らない奴と寝るなんて、この上ない恐怖である。
床やソファで寝るのは嫌だったから、仕方なくわたしは、ベッドに入った。
「いいお湯だったよ。千歳も入ったら?」
「ちょっと、自分の家みたいに言わないでよ。ていうか、わたしは入らないから」
「入らないって、…不潔だな」
「女の子にそんなこと言わないの。嫌われるよ」
「いやいや、ごめん。お願いだから嫌わないで」
彼の必死さに、わたしは思わず吹き出しそうになる。
「あんたのこと、嫌いはしないけど、相当怪しんでるよ」
「まぁ、そうだろうね」
彼は勝手にわたしのベッドに身を投げて、ボフンと音を立てて沈めた。
「もー、わたしの寝るとこ無くなるじゃん」
「え?本当は一緒に寝れるって喜んでるくせに」
「喜んで無いし」
そもそも、よく知らない奴と寝るなんて、この上ない恐怖である。
床やソファで寝るのは嫌だったから、仕方なくわたしは、ベッドに入った。