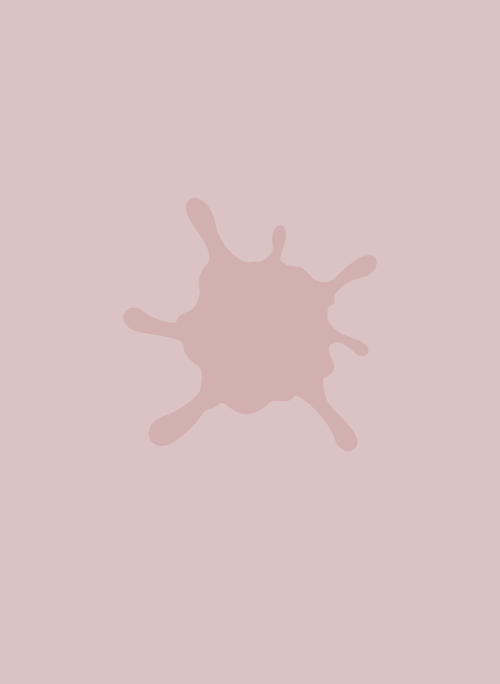***
一陣の風が、沢を渡っていった。
片目に白い眼帯を貼った修験者は、その額に浮いた汗を拭った。背負ったみやげが、ずっしりと重い。
山の湧き出る清泉の、その源泉よりも清らかな禁域で育った少女が、初めて漬けた味噌だという。
少しだけ大人びて、はにかんだ笑顔で嬉しそうに、届けて欲しいと託された味噌だ。
隻眼の修験者は、沢の水で喉を潤し、空を見上げた。
紅葉の隙間から見た青い空に、大きな白い鳥の影が一声鳴いた。
「そう急かすな。まだ日は高い。草木が眠る前までには、ちゃんと着くだろうよ」
修験者は重い荷物を背負い直して、歩き始めた。
水鏡のほとりに立つ、クチナシの古木に、少女の想いを届けるために。