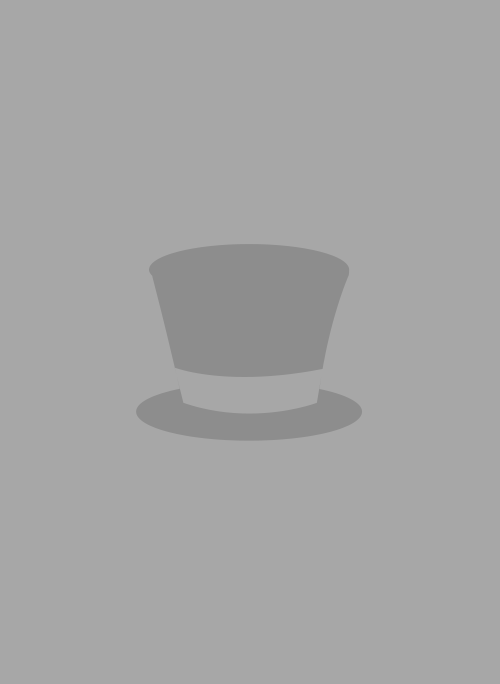「ああ、いいお湯だった。冷蔵庫に野菜ジュースあったよね?」
湯上がりで頬を桃色に染めた彼女の声も、今は耳に入らない。
アツシ……くそう……一体どんなやつなんだ。
その時はまだ、浮気だと断定するには材料が少なかった。
だが、要注意人物には違いない。
少なくとも、アツシという男は彼女に惚れているのだから――。
太田はそれ以来、事あるごとに彼女のメールを盗み見るのが癖になった。
最初は少なかったメールの数もどんどん増えてきて、会話もずいぶんと親しげになってきている。
携帯を握りしめ、奥歯を噛みしめる太田。
それでも、彼女を問いつめることはできなかった。
メールを盗み見ていることを打ち明けるのは、プライドが許さなかったのだ。