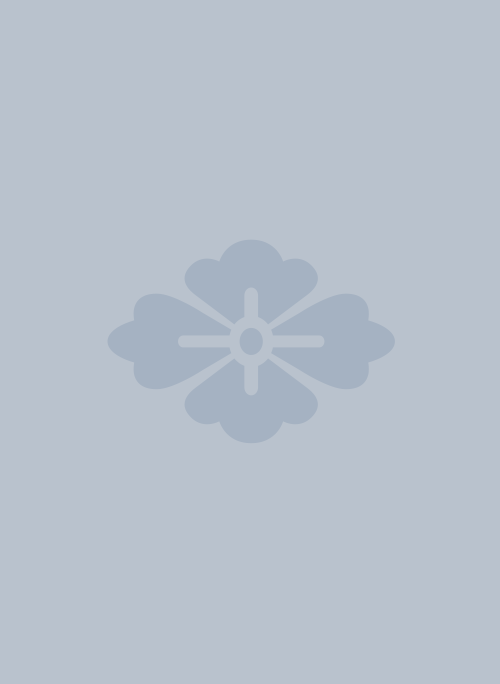「えっ?あるって……離岸流に流されたことが?」
そんなこと体験したらどう頑張っても忘れられそうにないけど…。
「そう。そん時さ、いつもは砂場で見守ってくれてた母さん達は自販機に飲み物買いに行っててさ。その場にいたのは、俺とあおとお姉さんの3人だけ。それに、元々あまり人がたくさん来るような海じゃなかったからさ。俺ら以外に人はいなかった。」
「それで、その母さん達が留守の間に俺が離岸流に流されたの?」
「うんそう。未だに何でかは分からないんだけど、あおが唐突に海に向かって走って行ってさ。何か光ってる!とか言いながらズンズン海に入って行っちゃって」
「宝物を見つけた子供かよ。」
どちらかと言えば、陽人の方がそういうことしそうだけど…まさか俺がそんなこと…(失礼)。
「…まぁ子供だったから。そしたらそこからはあっという間にあおが沖合まで流されてさ、もう本当に一瞬で。助けてーって言いながら沈みかけてて。」
陽人の強く握った拳が震えてるのを見て、今までずっとトラウマとして陽人の胸に刻まれていた事件なんだと悟った。
「あおが離岸流に巻き込まれてるってお姉さんが叫んだのを聞いた瞬間さ、俺怖くて。あおがいなくなっちゃうかもって思って怖かったのももちろんあったけど、真っ先に飛び込んで助けないといけないのに、俺まで流されたら…って思ったら足が動かなくてさ。……俺にはあおを助けられなかった。」
「ほんと、最低だよな。覚えてなかったと言えど、今まで黙っててごめん。」
「いや、普通怖いのが当たり前だろ。俺が勝手に飛び込んだんだから、お前が気にすることじゃないだろ。」
「……おう。」
困ったように軽く笑ったあと、小さくありがとなって呟いた気がした。
「……でもさ、お姉さんは俺とは違ったんだ。」
「えっ?それって、まさか、」
嫌な予感が頭をよぎり、心臓がドクドクと忙しなく騒ぎ出す。
「そのまさか。お前を助けようと海に飛び込んだんだ。お姉さんは海の知識も豊富だったし、泳ぐのも得意だった。その頃の俺は心底安心した。あぁ、お姉さんがあおを助けてくれるって。」
「─────けど、お姉さんだってまだ中学生だ。あおのことは助けられたけど、自力で浜辺まで戻ってこれるほどの体力は残っていなかったんだ。」
「そんな……」
「俺だって、何も指くわえてその状況を見てたわけじゃない。中身を捨てて空になったペットボトルを投げたり、俺の浮き輪だって投げた。声を張り上げて助けも呼んだ。ガキの俺が思いつく限りのことは全部やった。」
陽人は一度言葉を切って、もう一度続けた。
「でも、結局お姉さんを助けることはできなかった。お姉さんはあおを助けた時点でもう結構沖合まで流されていて、ペットボトルを投げようが、浮き輪を投げようが、小学生の俺が投げられる距離なんかたかが知れていて。全然届かなかった。」
俺は言葉を紡ぐことができず、ただ、陽人の話を理解しようとすることだけに必死だった。
「いくら声を上げても、周りに人がいなくちゃ、聞こえなくちゃ意味がない。5分後くらいにやっと母さん達が帰ってきたけど、もう遅かった。お姉さんは体力についに限界がきて、海に沈んでいった。」
「………10年経った今でも、お姉さんの遺体は見つかってない。」
「俺は、あおの時も、お姉さんの時も無力だった。なにもできなかった。ただ命を見捨てただけ。」
まるで懺悔のように、陽人は一言一言絞り出すように口に出した。
「それは、違うだろ。お前が気に病むことじゃない。俺のこそ、命まで助けてくれた人のことを忘れるなんて、それこそ、…。今まで、陽人1人に辛い思いさせてごめん。」