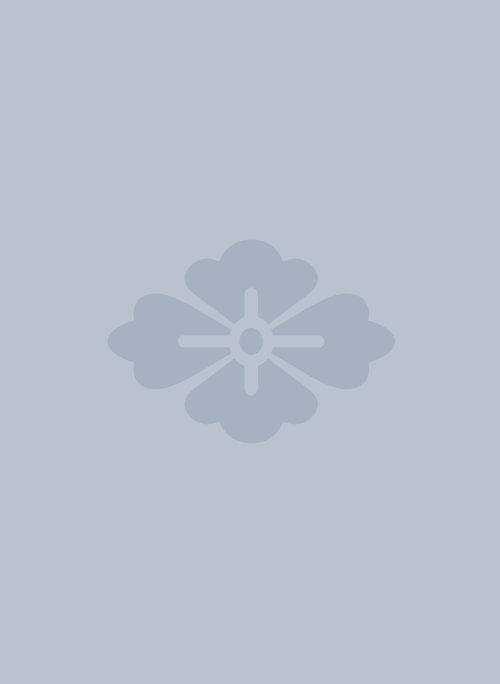「これは…言うつもりは無かったんだが……雪、俺では駄目か?」
私を包み込みながら一君はそう聞いた。
質問の意味がわからず少しだけ顔を上げて一君を見上げる。
「総司じゃなくて、俺にしないか?俺はずっとお前が好きだったんだ」
「冗談…だよね?」
思わず口から溢れたが一君の目は真剣そのもので、冗談でない事が分かる。
「弱っている時に言うのは我ながら姑息だとは思う。だが、惚れた女が辛い思いをしている時に駆けつけてやれないのは嫌なんだ」
一君の腕をほどき腰に挿してある刀に視線を向けると前に四人で出かけた時に買ってくれた鐔が目に入る。
それを一撫ですると顔を再び一君に向けた。
「一君の事は好き。でもあなたの好きとは違う。だから…ごめん」