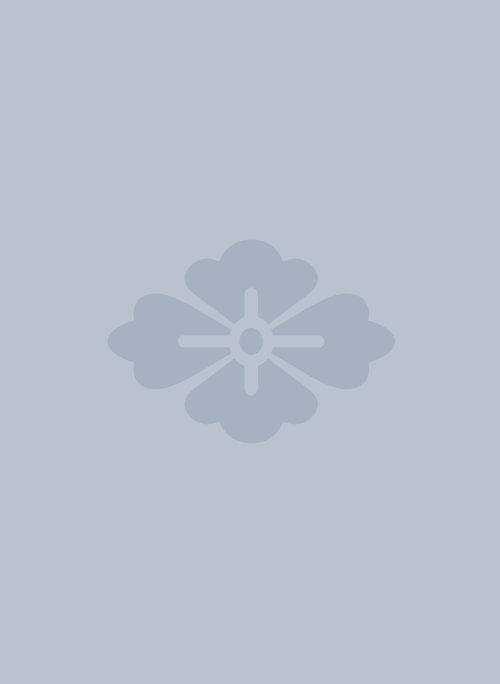「初めて会った時、お前は見ず知らずの俺を助けただろう。あんなことしたって何の利にもならないというのに」
「……だって、私のお父さんは周助先生で兄は勇さんだよ?筋金入りのお人好し一家だから…私達からしたら普通だよ」
「仮にそれが近藤家の普通だとしても、俺がお前に助けられたのは事実だ。だから俺はお前を助けたい。何があったのか話してくれなければ、俺はお前を助けることもできない」
真剣にそう言ってくれた一君に遂に私は涙を見せた。
助けて欲しかった。
話を聞いてもらいたかった。
でも誰にも話せなくて、総司の病が進行するにつれて私達の距離も離れていった。
日を追うごとに総司を失う恐怖と孤独感は強くなる。
泣きじゃくる私を一君は落ち着くまで抱きしめてくれていた。