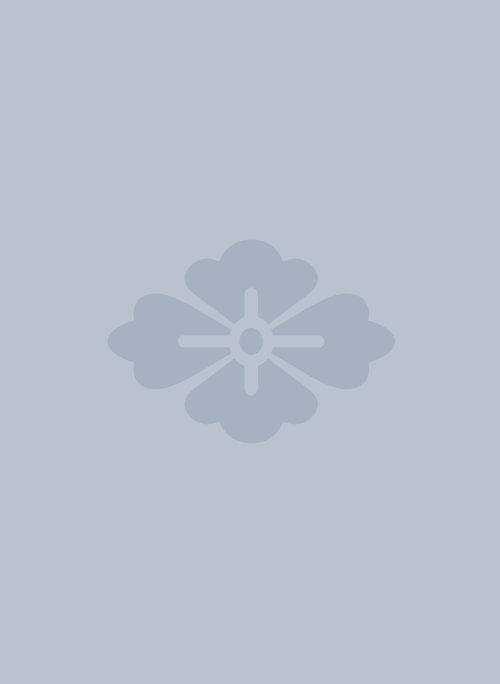蝸牛に話しかける私を笑う事も蔑む事もせず、一君は黙って私の言葉に耳を傾けていた。
蝸牛は怯えているのかツノを縮めてしまった。
可哀想なので仕方なく元の場所へ戻すと目の前を流れる川へ目を向ける。
「一君はさ、何でいつも私を助けてくれるの?あの時も…私はあんなに酷いことを言ったのに、何で今も側にいてくれるの?」
心情の読めない表情を浮かべる一君をジッと見つめる。
「お前に助けられたからだ」
「私に?」
そんなはずはない。
いつだって私の方が助けられてばかりだ。
私は何もしていない。
疑うような眼差しを向けていたからだろうか、珍しく一君は口元を綻ばせた。